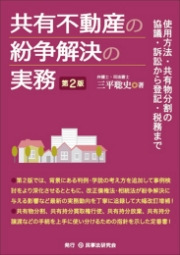【不動産売買;売主の代表権がないと無効,表見代理】
1 不動産を購入しても売主の会社代表者の代表権がないと無効となる
会社が売主、という場合、会社内部の事情によって「売買契約の効力」が後から無効となる場合があります。
会社の法律行為が無効となる例
・売買契約は代表取締役Bが締結などの手続を行った
・会社の商業登記上、代表取締役としてBがしっかりと登記されていた
・不動産の所有権移転登記(A→C)も行った
・その後、Aを取締役に選任した株主総会決議が訴訟により無効とされた
株主総会決議取消訴訟、決議不存在確認訴訟、決議無効確認訴訟など
※会社法830条、831条
ここで「株主総会決議取消訴訟」「決議不存在確認訴訟」「決議無効確認訴訟」の判決の効果は遡及効があります。
一定の無効や取消の効果は訴求しない(将来効)とされていますが、これらの訴訟は除外されているのです(会社法839条、最高裁昭和44年7月10日第一小法廷判決等)。
逆に、判決の効力は第三者にも広く及ぶとされています(対世効;会社法838条)。
そうすると、Cはまったく権利のない者と契約したということになります。
理論的にCは所有権を取得していないことになります。
不動産登記も真の所有者であるAに返さなければならないことになります。
2 被害者の買主の所有権が否定されない場合もある
原則として被害者であるCは所有権を得られません。
しかし、買主が商業登記上の代表者を信用したのに所有権を得られないのは不合理ということもあります。
そこで、例外的に救済される場合もあります。
この点、法的根拠としてはやや一般的な規定の「類推適用」を用います。
無権利者からの購入者を保護する規定
あ 商業登記への信用保護
※会社法908条2項
い 表見代表取締役;後掲判例1
※会社法354条
う 民法上の無権代理の規定
※民法109、110、112条
これらをまとめて「表見代理」と言います。
参考情報
3 被害者の買主は「善意、無過失」であれば保護される
原則的に所有権が得られない被害者が例外的に所有権を得られる要件を説明します。
法的根拠はいくつかありますが、基準自体は同様です。
被害者の買主が保護される要件
あ 買主(C)が、契約を締結した者が権限がないことを知らない、かつ、知らないことに過失がない
→「善意無過失」と言います。
い 売主(A)が、Cの誤解を生じる原因作成に関与している
→「帰責事由」と言います。
実際には、個別的な状況を元に↓のようなことが分かる状況だったかどうか、が判断の元になります。
善意無過失の判断要素
あ 商業登記上、最近役員が全員入れ替わっている
不正な総会決議があったのではないかと疑われる
い 以前から個人的、仕事上の付き合いがあった
売主の会社の役員構成などを把握していたはず(後掲裁判例2)
帰責事由は多くの事情から判断されます。
帰責事由の判断要素
あ 虚偽の呼称の黙認
実際の役員などが仮装の代表者が代表者と称することを黙認していた
い 残存登記の放置
実際の役員などが以前の役員が登記上残存している状態を放置していた
4 表見代理の適用が判断された裁判例
実際の裁判で、表見代理の適用の有無が判断されたケースをまとめておきます。
表見代理に関する裁判例の事案概要;後掲判例1〜4
一般的な表見代表取締役の規定の類推適用を認めた
・裁判例2
以前からの個人的、仕事上の付き合いがった
→表見代理の適用を否定した
・裁判例3
売主の会社内の関係者が仮装の代表者の外観作出に関与していた
→会社法354条の類推適用を肯定した
・裁判例4
売主の会社に「帰責事由」がないとされた
→表見代理の適用を否定した
5 判例の引用
(1)判例1・一般的な表見代表取締役の類推適用
判例1・一般的な表見代表取締役の類推適用
※最判昭和56年4月24日
(2)判例2・表見代理の適用否定
判例2・表見代理の適用否定
2 争点(2)(Cが原告の代表権を有していると信じたことについての正当理由の有無)について
(1) そこで,次に,被告の代表取締役であったDが,本件信託契約締結にあたり,Cが原告の代表権を有していると信じたことについて正当な理由(善意・無過失)があるといえるかについて検討する。
(2) 証拠(甲24,69ないし71,73,74)及び弁論の全趣旨によれば,DとCは,ともに大阪出身の同郷で,幼少のころからの知り合いであり,その後東京で仕事上の付き合いが始まり,平成20年10月には,いずれも被告設立の発起人として,被告の普通株式各5株ずつを各5万円で引き受け,共同で被告を資本金10万円で設立したこと,被告の設立後は,Dが被告の代表取締役に就任し,Cが被告の従業員として稼働していたこと,被告の社内において原告と本件各不動産について本件信託契約を締結する旨意思決定したのは,D,C及びB(被告現代表者)であること,以上のとおり認められる。
上記認定事実から認められるDとCの親密な関係からすれば,被告の代表取締役であったDは,本件信託契約の締結にあたり,Cが原告の代表取締役ではないことについて悪意であったと推認することができ,かかる推認を覆すに足りる証拠はない。
(3) なお,仮に,本件信託契約締結の際に,Cが原告の代表取締役ではないことについて,被告のDが悪意であったとは認められないとしても,前記前提事実のとおり,本件信託契約が締結された当時,原告の商業登記簿上は,原告の代表取締役及び取締役はめまぐるしく変わっていたのであるから,Dとしては,本件信託契約締結にあたり,直近の原告の商業登記簿謄本を確認し,それによって,Cが原告の代表取締役ではないことを知り得たはずであるのに,直近の原告の商業登記簿謄本を確認することを怠ったものであるから,被告のDは,本件信託契約の締結にあたり,Cが原告の代表取締役ではないことについて少なくとも善意・有過失であったことは明らかである。
(4) したがって,本件信託契約については民法109条の表見代理は成立せず,本件信託契約は無効(原告被告間に効果帰属しない)である。
※東京地判平成24年9月13日
(3)判例3・会社法354条の類推適用を肯定した
判例3・会社法354条の類推適用を肯定した
(1)上記2(2)イで認定したとおり,本件売買契約当時も,登記上,Gが原告の代表取締役である旨登記されていたと認められるところ,同人について有効な代表取締役の選任決議がなかったとしても,会社の代表取締役として登記された者が代表取締役としてした行為については,会社法354条の類推適用により,善意の第三者に対してその責に任ずべきものと解される(最判昭和56年4月24日裁判集民事132号585頁参照)。そこで,被告Y1において,Gが真実は代表取締役ではなかったと知っていたかについて,検討する。
(2)原告は,前記2(1)イで主張したように,本件売買契約が不自然であり,特に,平成20年11月には,原告の現在の代表者であるAからGに対し,訴訟等により原告の株式の74%をAらが取得したので,原告の資産の処分等の重要な事項の決定は慎むよう警告する文書を送付していること(甲17の1及び2)から,Hらが原告の実質的支配を失う前に,原告所有の不動産の所有権名義を第三者に移転してしまおうと考え,息子である被告Y1に本件土地建物を売却したのであり,Gや被告Y1には,事情を話して取引をしたはずであるから,被告が善意であることはあり得ないと主張する。
(3)しかしながら,乙19(被告Y1の陳述書)によると,被告Y1は,本件売買契約当時,Gが原告の代表取締役であると思っていたと述べているところ,前記のとおり,被告Y1は,原告の設立当初の代表取締役であったHの息子である(当事者間に争いがない。)が,甲16(株主名簿)上も原告の株主となったことはなく,また,原告の役員となったこともなく,原告の業務に関与したことを伺わせる証拠の提出もないこと,上記認定のとおり,Gが代表取締役に選任されたことは認めがたいものの,前記2(2)イで認定したとおり,本件売買契約当時も,Gが原告の代表取締役として行動していたことが認められ,乙19(被告Y1の陳述書)によると,被告Y1は,上記HからGが原告の代表取締役であると聞かされていたと述べており,当時の原告を実質的に支配していたのはHであったのであるから,むしろ,被告Y1としては,それを疑うべき事情を認識できたとはいえなかったと認められる。
また,原告主張の警告(甲17の1)の内容は,その時点でAらが原告の株式の多数を取得するに至ったことから,Hが原告の支配権を失うことになったので,原告の資産の処分等の重要な事項の決定は慎むようにされたいというものであって,確かに,この警告を受けて,原告がHの身内に原告所有の不動産を売却していった可能性も疑われるが,仮に,G及びHがそのことを被告Y1に説明したとしても,その結果,被告Y1が原告やその債権者を害する可能性があることを認識することはあっても,そのことから,それまで代表取締役登記がされていたGの選任手続が行われていないとか,その手続に瑕疵があったことなどを説明した,あるいはそれを認識し得たということには必ずしも結びつかない。
以上によれば,被告Y1が,本件売買契約当時,Gが原告の代表取締役でなかったことを知っていたとまでは認めるに足りない。
(4)前記2(1)のとおり,本件売買契約の事実は認められ,同契約が通謀虚偽表示であるとは認めがたい。そうすると,会社法354条の類推適用により,原告は,被告Y1対し,Gが原告の代表取締役ではなかったことを対抗できないから,原告の被告Y1に対する本件売買契約により,原告は本件土地建物の所有権を喪失したと認められる。
4 よって,その余の点を判断するまでもなく,原告の本訴請求はいずれも理由がない。
※東京地判平成24年3月8日
(4)判例4・表見代理の適用否定
判例4・表見代理の適用否定
1 民法109条の適用ないし類推適用について
(1) 被告は,Cの本件各設定契約締結行為の際,原告が,本件虚偽登記をすることにより,被告に対し,Cに代表権(代理権)を授与したことを表示した,あるいは,原告が本件虚偽登記をしたのではないとしても,それと同視できる行為をしたことにより自ら表示したと解すべきであると主張するようである。
(2) しかし,前記第2,1(4)及び(5)の事実によれば,本件各設定契約当時,原告の真正な代表取締役はAであったところ,本件全証拠によっても,Aが,Cについて,原告の代表取締役であるとの登記をした事実を認めることができない。
(3)ア また,被告は,原告が本件虚偽登記をしたと同視できる行為として,Cに原告の名義を冒用されるおそれが非常に高い状況にあり,それを原告が認識しながら,原告の役員変更登記を4か月も怠った行為を挙げる。
イ 確かに,前記第2,1(4)及び(5)の事実のほか,証拠(甲12,乙6)によれば,平成16年7月12日に,原告の代表取締役としてAが,取締役としてD及びE1がそれぞれ就任(重任)し,同月22日付けでその旨の登記がなされていたが,重任後2年を経過した後も役員変更登記がなされていなかったこと,その後,平成18年7月25日にAらが退任し,同年11月10日にCが代表取締役に,G及びFが取締役に就任した旨の本件虚偽登記申請が同年11月14日になされ,同日,その旨の登記がなされたことが認められる。
しかし,株式会社の代表取締役及び取締役の任期が満了した場合,新たに選任された代表取締役及び取締役が就任するまで,もとの代表取締役及び取締役が,一時代表取締役及び取締役としての権利義務を有するのであり,直ちに退任登記をしなかったからといって,権限のない者につき虚偽の登記を作出していたというものではない。
また,証拠(甲14,20,乙6)によれば,本件虚偽登記の申請には,平成18年7月25日にAらが任期満了により退任し,Cらが取締役に選任され,被選任者らが即時就任を承諾した旨記載された原告の平成18年11月10日付け株主総会議事録,代表取締役Aが資格喪失により退任し,後任代表取締役にCが選任され,同人が即時就任を承諾した旨記載された同日付け取締役会議事録が添付されていたが,上記株主総会は存在せず,したがって取締役会も無効であったこと,上記各議事録に使用された原告代表者印は原告の真正な登録印ではなく,また,Aがその使用を許したものでもなく,従前の真正な登録印が原告に無断で変更されたものであったこと,Aらは,平成18年11月20日ころ,本件虚偽登記がなされたことを知り,その後,まもなく,東京地方裁判所に対し,原告及びCらを債務者として,取締役の職務執行停止等の仮処分を申し立て,同年12月12日,原告及びCらにつき取締役あるいは代表取締役の職務の執行停止を命じ,職務代行者を選任する仮処分決定がなされたこと,さらに,Aらは,上記株主総会決議不存在確認等請求の別件訴訟を提起し,平成19年2月20日にその勝訴判決を得,それが確定したこと,そして,同判決に基づき,同年3月26日,Aらの役員退任登記が抹消され,各人の役員の地位が回復した旨が商業登記簿上記載されたこと,同日,商業登記簿上,Cらが取締役及び代表取締役から抹消されたこと,平成19年1月25日ころ,Aらは,Cが上記株主総会議事録及び取締役会議事録を偽造し,それを株式会社変更登記申請書等の書類とともに法務局に提出して,Cが原告の代表取締役に選任された旨の虚偽の登記申請をし,電磁的記録である商業登記簿ファイルに不実の記録をさせ,備え付けさせ公正証書の原本としての用に供したことなどを告訴事実として,電磁的公正証書原本等不実記録,同供用罪で告訴したことが認められ,これらの事実によれば,本件虚偽登記がなされた当時,原告の真正な代表取締役であったAや取締役であったD及びE1が,本件虚偽登記に何らかの形で関与したということもできない。
ウ そして,証拠(甲16,乙6)によれば,役員が任期満了し,役員変更登記(重任登記)が完了した場合であっても,その役員が株主総会の席上で口頭で辞任を申し出るか,同総会で同役員を解任する決議がなされたとするかし,その後,新たな役員を選任した旨の株主総会議事録を偽造し,その議事録を添付した役員変更登記申請をすることにより,虚偽の役員就任登記をすることが可能であることが認められ,この事実に照らせば,原告あるいは原告代表者のAが任期満了に伴う役員変更登記(重任登記)を怠ったから,本件虚偽登記がなされたといえる関係があるということはできない。
(4) 以上のほか,Cの本件各設定契約締結行為の際,原告が,本件虚偽登記をしたとか,それをしたのと同視できる行為をしたと認めるに足りる証拠はなく,民法109条を類推適用する要件となる何らかの授権表示があったということはできないから,その余の点について判断するまでもなく,被告の主張には理由がない。
2 会社法908条2項の類推適用について
(1) 被告は,Cの本件各設定契約締結行為の際,原告が,故意または過失により本件虚偽登記をしたので,その事項が虚偽であることをもって,本件各設定契約をした善意の被告に対抗できないと主張するようである。
(2) しかし,前記第2,1(4)及び(5)の事実によれば,本件各設定契約当時,原告の真正な代表取締役はAであったところ,本件全証拠によっても,Aが,Cについて,原告の代表取締役であるとの登記をした事実を認めることができない。
(3) また,前記1(3)イ及びウのとおり,原告あるいは原告代表者のAが故意または過失により本件虚偽登記をしたと同視できるような事実はなく,他にそのことを認めるに足りる証拠もない。
(4) よって,その余の点について判断するまでもなく,被告の主張には理由がない。
3 民法112条の類推適用について
(1) 被告は,Cが,昭和54年3月12日から平成2年12月10日までの間,原告の代表取締役の地位にあったことをもって民法112条の「代理権」とし,その消滅を第三者である被告に対抗できないと主張するようである。
(2)ア ところで,会社法908条1項は,商人の取引活動が,一般私人の場合に比し,大量的,反復的に行われ,一方これに利害関係をもつ第三者も不特定多数の広い範囲の者に及ぶことから,商人と第三者の利害の調整を図るために,登記事項を定め,一般私法である民法とは別に,特に登記について,登記事項を登記しない限りこれを善意の第三者に対抗できないとするとともに,登記後であれば第三者は正当な事由がない限りこれを否定することはできないという効力を付与したものである。
そして,株式会社の代表取締役の辞任及び代表資格の喪失は,会社法911条,909条によって登記事項とされているのであるから,前記同法908条1項の趣旨に鑑みれば,登記事項については専ら同法のみが適用され,登記後は,同条所定の「正当な事由」がない限り,善意の第三者にも対抗することができるのであって,別に民法112条を適用ないし類推適用する余地はないものと解すべきである。(最高裁判所昭和48年(オ)第142号昭和49年3月22日第2小法廷判決・民集28巻2号368頁参照)
イ これを本件について見るに,確かに,証拠(乙2の1の1及び2,2の2,2の3)によれば,原告は,昭和54年3月12日に設立し,Cは設立時以降,代表取締役及び取締役の地位にあったことは認められるが,他方,前記証拠に加え証拠(乙2の3から2の9まで)によれば,Cは,平成2年12月10日に原告の代表取締役及び取締役を辞任し,同日,Aが代表取締役及び取締役に就任し,平成3年1月30日,その旨の登記がされていること,Aは上記就任以降本件口頭弁論終結時まで,原告の代表取締役及び取締役の地位にあり,商業登記簿上,本件虚偽登記がされるまでは,その旨の登記がなされていたことが認められる。
したがって,被告が,平成2年12月10日にCが原告の代表者資格を喪失したことについての善意無過失を理由に民法112条を適用ないし類推適用して,原告に表見代理責任を追及することは許されないというべきである。
また,被告が,Cを原告の代表取締役として本件各設定契約をしたのは平成18年11月17日であり,その当時は本件虚偽登記が存在していたこと,本件各設定契約に基づく抵当権を担保とする金銭消費貸借契約の締結時まで原告と被告との間に何らかの取引があったことは窺われないことに照らせば,本件虚偽登記についての善意が問題になることはあっても(ただし,前記2において,908条2項の適用あるいは類推適用は認められないことは前述したとおりである。),被告が,平成3年1月30日付けのCの代表権喪失の登記についての善意が問題になるということはあり得ないし,その善意につき正当な理由があるとは到底思われない。
ウ よって,その余の点について判断するまでもなく,被告の主張には理由がない。
4 なお,被告は,本件各設定契約につき原告が責任を負う根拠として,会社法354条の規定,あるいは設立無効や合併無効の訴えに関する規定の適用ないし類推適用を挙げているが,いずれも具体的な請求原因事実の主張がないから,主張自体失当というべきである。
5 以上のとおり,本件各仮登記につき,登記原因となる本件各設定契約について原告が責任を負うとは認められず,本件各登記は登記原因を欠き,無効というべきであるから,原告の本件請求にはいずれも理由がある。
6 よって,原告の本件請求をいずれも認容し,訴訟費用の負担につき,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
※東京地判平成19年10月22日