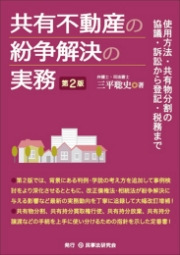【借地権譲渡許可の裁判の申立人と申立時期】
1 借地権譲渡許可の裁判の申立人と申立時期
借地権(賃借権)を譲渡する場合、地主(賃貸人)の承諾が必要です。この点、地主が承諾してくれない場合でも、(建物と)借地権を譲渡(売却)する方法があります。地主の承諾に代わる裁判所の許可です。
詳しくはこちら|借地権譲渡許可の裁判の趣旨と機能(許可の効力)
この借地権譲渡許可の裁判ですが、申し立てることができるのは誰か、また、どのタイミングで申し立てることができるのかということが問題になることがあります。本記事ではこれらについて説明します。
2 借地権譲渡許可の申立人(基本)
借地権譲渡許可の裁判の申立をすることができるのは、(譲渡前の)借地人です。譲り受ける予定の者(借地人候補者)が申立をすることはできません。これに関して、もともと借地人が複数人であり、借地権(の準共有持分)の譲受人がもともと借地人の1人であった場合には、譲受人が申立をすることを認める考え方も提唱されています。
借地権譲渡許可の申立人(基本)
あ 条文
借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。・・・
※借地借家法19条1項
い 要点
元の借地人(=譲渡人)が(譲渡前に)申し立てる
う 譲受人による申立
ア 原則→否定
建物の譲受人は譲渡等許可申立てをすることができない。
※澤野順彦編『実務解説 借地借家法 改訂版』青林書院2013年p250
イ 例外の可能性→準共有者間の譲渡
(注・借地権をBCDが準共有者しているところ、Dの準共有持分をBに譲渡するケースにおいて)
・・・ここでは従前借地契約の当事者であったBが当該契約の継続のために申立てを行うのであり、「借地権者」を広く解して、持分の取得者である準共有者の申立てを認める解釈も可能と思われる。
※吉原知志稿/潮見佳男ほか編著『Before/After民法・不動産登記法改正』弘文堂2023年p61
3 賃借人と転借人による共同申立(肯定)
単純な賃貸借ではなく、2つの賃貸借が連続している(転貸借)ケースで、特殊な譲渡の方法がとられた事案があります。賃借人Aと転借人Bが同時に第三者Cに賃借権と建物を譲渡する、というケースです。結果的に転貸借は解消され、単純な賃貸借になるというものです。
借地権譲渡許可をAとBが共同で申し立てたことについて、これを適法と認めた裁判例があります。なお、その判断を批判する見解もあります。
賃借人と転借人による共同申立(肯定)
あ 想定する譲渡の内容
A=借地人(賃借人)
B=転借地人(転借人)=建物所有者
Aが第三者Cに借地権(賃借権)を譲渡する
BがCに建物を譲渡する
その結果、Cが借地人かつ建物所有者となる
い 裁判例
ア 事案
本件土地の転借人たるBが右土地上の本件建物を件外C株式会社(以下「C」という。)に譲渡するのに伴い、Cに対し、Aが本件賃借権を譲渡し、Bが本件転借権を譲渡する許可を求めるというものであるが、・・・、BはAの先代亡朝田幸一が設立して経営していた同族会社であって、Aの一族が役員を占め現在も極めて密接な関係を有していること、A及びBはそれぞれ本件賃借権又は本件建物をどちらかに譲渡することによって本件転貸借関係を終了させる用意がある旨陳述しており、本件転貸借関係の維持を望んでいないこと及びCはAから本件賃借権を譲受ける意向であることが認められるから、A及びBは、賃借人たるAが本件賃借権を、転借人たるBが本件建物を、それぞれCに譲渡する趣旨で本件各申立を行っているものと認められる。
イ 判断
そして、このような申立も、AとBが共同して申立をしている以上、抗告人になんら不利益を与えるものではないから適法であり、AとBは本件各申立の適格を有するというべきである。
※大阪高決平成2年3月23日
う 批判
判決の結論は疑問である
※澤野順彦『実務解説 借地借家法』青林書院p249
4 借地権譲渡許可の申立時期(基本)
次に、借地権譲渡許可の申立のタイミングについて説明します。まずは条文の規定と解釈論のうち基本的部分を整理しておきます。
条文の文言は、譲渡「しようとする」場合、となっているので、譲渡する前に申し立てる必要がある、ということになります。譲渡の後に申し立てた場合は不適法として却下されてしまいます。具体的には、建物の所有権移転登記がなされてしまうと通常、借地権も譲渡したということになります。
借地権譲渡許可の申立時期(基本)
あ 条文・規定
| 規定・文言 | 条文 |
| 『譲渡しようとする場合』 | 借地借家法19条1項 |
| (参考)『譲渡セントスル場合』 | 借地法9条ノ2第1項 |
い 譲渡後の申立の却下
借地権の譲渡後に譲渡許可の申立をした場合
→不適法である
→却下となる
※東京地裁昭和43年3月4日
※東京高裁昭和45年9月17日
※香川保一『法曹時報』18巻11号p71
う 譲渡後と判断される典型例
建物について所有権移転登記がされた場合
→原則的に建物・借地権の譲渡があったと認める
※澤野順彦『実務解説 借地借家法』青林書院p248
詳しくはこちら|借地上の建物の譲渡は借地権譲渡に該当する
5 借地権譲渡後の申立を認める見解(実務では否定)
前述のように、借地権譲渡許可の申立をすることができるのは、(建物・借地権の)譲渡前でなくてはなりません。しかし、譲渡後の申立を認めた上で、申立が遅れたことは不利な事情(許可しない方向)の1つと位置づける、という見解もあります。ただし、このような見解は裁判所では採用していません。
借地権譲渡後の申立を認める見解(実務では否定)
あ 譲渡前の申立
譲受人が誰かが特定できていない
→この状態で申立をすることになる
い 緩和的な見解
譲渡前という規定は原則の申立時期という意味である
譲渡後の申立も形式的には適法である
一切の事情の1つとして考慮することになる
※借地借家法19条2項
※星野英一『借地・借家法/法律学全集』有斐閣p308
※加藤正男ほか『基本法コンメンタール 借地借家法』p218
※鈴木禄弥ほか『新版 注釈民法(15)』有斐閣p529
※稻本洋之助ほか『コンメンタール借地借家法 第3版』日本評論社p141
6 建物(借地権)の遺贈における例外的な申立時期
遺贈については、受遺者(権利を取得する者)が相続人以外である場合は借地権譲渡として扱われます。ここで、遺贈の効果が発生するのは被相続人が亡くなった時です。譲渡前とは、亡くなる前ということになります。遺言は誰にも明かさないことも多いですし、また、いったん遺言を作成した後に自由に撤回や変更をすることが認められています。生前に地主の承諾を得ることや裁判所の許可を申し立てることは非現実的です。そこで例外的に、亡くなった後に、相続人や遺言執行者が借地権譲渡許可の申立をすることが認められます。
建物(借地権)の遺贈における例外的な申立時期
あ 遺贈と借地権譲渡(前提)
相続人以外の者へ遺贈により借地権が移転した
→原則として借地権譲渡に該当する
詳しくはこちら|賃借権の相続・遺産分割・死因贈与・遺贈は賃借権譲渡に該当するか
い 申立時期に関する裁判例
ア 原則論
借地法九条の二第一項に基づく借地権譲渡等許可の申立は、同条項の規定の文言及び民法六一二条一項の趣旨に照らし、賃借権の譲渡又は賃借物の転貸をするに先立つてなされなければならないと解すべきではあるが、
イ 遺贈の場合の例外
借地人が賃借地上の所有建物を遺贈する場合についてまでそれに伴う土地賃借権譲渡につき遺贈の効力発生前に、賃貸人の承諾又はこれに代る裁判所の許可を求めることを借地人に要求するのは、遺贈の性質上極めて不当というべきであり、この場合は、遺贈の効力が発生した後、その相続人又は遺言執行者による目的物件の引渡又は所有権移転登記に先立つて借地権譲渡についての賃貸人の承諾又はこれに代る裁判所の許可を求めれば足りると解するのが相当である。
ウ あてはめ
これを本件につきみるに、先に認定したとおり、Tは現に本件建物に居住して占有してはいるけれども、それは、本件建物に居住していたHの意思に基づいて同人と同居していたTがH死亡後も事実上居住を続けているに過ぎず、同人の遺言執行者たる相手方が遺贈目的物としてTに引渡したことに基づくものではなく、また、本件建物所有権のHからTへの移転についても、いまだ登記を経由していないのであるから、相手方の本件借地権譲渡許可の申立は適法というべきである。
※東京高判昭和55年2月13日
本記事では、借地権譲渡許可の裁判の申立に関して、申立人と申立時期を説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法が違ってきます。
実際に借地権(借地上の建物)の譲渡に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。