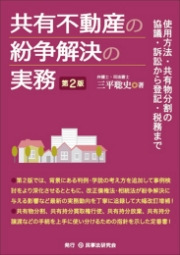【総合方式と賃料試算の4手法の合理性を否定した裁判例(平成14年東京高判)】
1 総合方式と賃料試算の4手法の合理性を否定した裁判例(平成14年東京高判)
2 賃料試算の4手法を否定する部分
3 減額請求自体を否定する部分(結論)
1 総合方式と賃料試算の4手法の合理性を否定した裁判例(平成14年東京高判)
継続賃料の算定では4手法の試算賃料を総合的に判断する総合方式が用いられています。
詳しくはこちら|改定賃料算定の総合方式(一般的な比重配分の傾向や目安)
4つの相当賃料の試算手法について,不合理性を指摘し,いずれも用いなかった裁判例があります。
本記事ではこの判決の主要部分を紹介(引用)します。
2 賃料試算の4手法を否定する部分
この判決のもっとも特徴的なところは,裁判実務でメジャーな4つの算定方式のすべてを採用しない,と判断しているところです。
<賃料試算の4手法を否定する部分>
6 原審における鑑定の評価
原審鑑定人飯田行雄は,本件の地代の額について金一三五万六〇〇〇円を相当とする鑑定書を提出している。原判決は,この鑑定結果を採用しているのであるが,その鑑定の手法として採用された利回り法,比準賃料,スライド法,差額配分法については,次のような疑問があり,結論として,この鑑定結果を採用することができない。
(1) 利回り法について
鑑定人は,利回りを乗ずるべき基礎価額は,土地の価格から借地権価格を控除した金額によるべきものとしている。しかし,本来借地権価格とは,賃借人に借り得があるとき,すなわち適正な地代と実際の地代の差額があるときに,その差額を資本還元した価格である。したがって,適正な地代の額と実際支払地代の間に差がなく,賃借人に借り得がなければ,借地権はあっても借地権価格は存在しない(そのことを判示する東京高裁平成一二年七月一八日判決金融商事判例一〇九七号三頁及び東京高裁平成一三年一二月二〇日判決金融商事判例一一三四号一三頁参照)。当事者双方に偏らない公平な立場に立って,適正な地代を計算しようとするときに,その計算の基礎となる額について,賃借人の借り得分を減額するということでは,その計算の結果算出される額が,合理的な理由もなく賃借人に有利になるということを意味する。そのような算出方法は,公平なものとはいえず,採用することができない。
前述のとおり,従前,土地の市場価格は,土地の収益還元価格を大きく上回る土地の値上がり期待部分を含んでいた。そのような時代に,土地の市場価格を基礎価格として,利回り法を適用すると,地代は,値上がり期待部分があるために,適正に算定することができない。そこで,市場価格より値上がり期待部分を除き収益還元価格分を算出して,これに利回りを乗じることにより地代を算出する必要があった。その値上がり期待部分の額を控除するのに,その代替手段として,これに近似するものと考えて,借地権価格分を控除するという手法をとったものである可能性がある。そうだとすれば,いくらかの合理性を肯定することができたかもしれない。
しかし,バブル崩壊以降の土地の市場価格は,前述2(1)記載のとおり,従前の値上がり期待部分が時間を追うにつれ減少しつつある。そのような中で,値上がり期待部分が大きかった時代に形成された借地権割合によって,借地権価格を計算して,市場価格より控除すれば,基礎価額は,土地の収益還元価格より低額となる可能性が生じる。それによって,地代を計算すれば,地代は過小評価されることになる。
もともと利回り法は,本来土地の市場価格が収益還元価格によって形成される場合に初めて,正当な地代計算方法たりうるものなのである。したがって,利回り法を使うのであれば,その中にどの程度の値上がり期待部分があるか不明な土地の市場価格を基礎価格とするべきではなく,収益還元価格を算出し,それをそのまま,すなわち,借地権価格を控除しないで,基礎価格とするべきなのである。
(2) 比準賃料について
比準賃料は,それが地代の適正額に関する相場を意味するものであれば,地代算定上は,もっとも重視すべきものである。それゆえ,できる限り広く事例を収集して,適正な地代の額の相場を発見するように努めるべきである。しかし,本件鑑定で収集された事例は,極めて少数にとどまり(前訴ではこのように少数ではなかった。),しかも非堅固建物の例ですましている。本件賃貸借でも,非堅固建物の時代と,堅固建物となってからでは,地代の水準が全く違っている(ほぼ三倍になっている。)。このように,少数のしかも性質が大きく異なる事例を収集しただけで,比準するのは危険であり,その鑑定結果に信をおくことはできない。
なお,前述2(3)記載のとおり,土地の地代の増減をめぐる賃貸人及び賃借人の交渉力は,現実には限られたものである。そのため,地代が適正な額と隔たっていても,それが当事者間の交渉で適正化されているとは限らない。そのため,継続地代の事例を収集しても,これがそのまま適正な地代の額であるとは限らないのであり,これとの比較をしても,意味のない結果に終わることがあることを,考慮に入れておくべきである。
地代が自由な競争によって形成されるのは,新規に土地の賃貸借が行われるとき,あるいは,建物収益(賃料)の低下があって,それを元に算定される適正地代の額が従前の地代の額を下回るなどのため,地代減額の強い圧力が生じて,当事者間の交渉により減額されるときである(そのため継続賃料の方が新規賃料より高額であるという事態が起こりうる。商業地の建物賃料では現にそのような事例も見られる。)。そのような新規地代あるいは建物賃料から算出される地代の合意例が収集されれば,それは,自由な競争によって形成された地代として,尊重されるべきである。しかし,将来そのような事例が集積されるまで,適切な事例を相当数収集することは困難なことであって,比準賃料には,このような問題がある。
(3) スライド法について
2の(4)記載のとおり,商業地の実態調査の結果によれば,全体のほぼ七七%は,地代に変動がなく,その残りは,値下がりした事例と,値上がりした事例で,その数に大きな差が見られない。そうすると,地代の世間相場の変動率は,広い地域で見れば,ほとんど〇に近いということになる(乙3参照)。ところが,本件鑑定では,スライド法の結果として,18.43%下落させている。これは固定資産税額の変動をそのまま反映させた結果であるが,固定資産税は,前述のように,経済外的な理由で増減しているのであり,固定資産税の増減があっても,そのことは地代を増減すべき経済的諸条件があることを意味しない。前述の実態調査の事例でも,固定資産税の変動がある事例が多数含まれているであろうが,結果として,地代の変動率は〇に近いのであるが,これはそのことを示しているものと考えられる。以上のことを考慮すると,このような算定方法には疑問があって採用することができない。
(4) 差額配分法について
差額配分法は,土地の市場価格が収益還元価格と乖離して変動していた過去の時代に,土地の市場価格を基礎にして算定される地代と実際支払い地代との差額を,賃貸人と賃借人間で配分するという思想で作られていた。しかし,それがなにがゆえに正当なのかを検証することは,極めて困難であった。現在は,土地の市場価格のうち将来の値上がり期待部分が減少し,次第に収益還元価格に近づこうとしているのであって,そうであれば,土地の収益還元価格を計算して,それによって適正な地代を算出すればたりるのであり,差額配分法の存在意義を認めることは困難である。そして差額配分法の正当性に,前述のような問題点があることを考慮すると,このような手法による算定結果を尊重するべきものかどうか疑問であり,参考に値しないものといわねばならない。
※東京高裁平成14年10月22日
3 減額請求自体を否定する部分(結論)
この判決では,4つの算定手法をすべて否定したので,どのように相当賃料(継続賃料)を計算するのか,ということが気になるところです。なんと,結論は減額自体を認めない,というものでした。むしろ,計算できないという時点で,賃料額維持の結論しかとれないといえるかもしれません。
<減額請求自体を否定する部分(結論)>
7 地代の適正額の水準について
以上のとおりであって,本件では,被控訴人が減額の意思表示をした平成一二年五月一〇日時点での適正な地代額を認定するに足る証拠はないものといわねばならない。
そして,前記認定のとおり,本件土地の市場価格の下落にもかかわらず,地代の額は増額されたのであり,それは,前述のように,過去の地代の額と適正な地代の額の間に格差があって,賃借人の借り得があり,適正な地代にするにはさらに増額する余地があったからにほかならないものと認められる。
そして,そのことは,前記認定の経過にあるように,現在の地代の額が決められた平成六年以降も,なお地代を増額すべきであるとの鑑定結果があったことによっても,裏付けられているといえる。
また,本件地代について鑑定したすべての鑑定人が,本件の借地権には,高額の借地権価格が存在することを前提にしているが,そのことは,前述のように,現在の地代の額でも,賃借人には借り得があり,それを資本還元すると,大きな金額にのぼることを意味している。
このような本件賃貸借の過去の経過や現状からすると,現在の地代の額は,なお適正な地代額から見て,低額である可能性がある。そうではなく,すでに適正な地代の額は,現在の地代の額を下回っているというのであれば,そのことを証するには,当裁判所が勧告したように,地上建物の賃料収入額を開示して,土地残余法により,適正地代の額を算出し,これと現在の地代の額とを比較検討するほかなく,それ以上に説得力のある方法は,発見することができない。
ところが,被控訴人は,このような開示を拒み,適正な地代額の計算の道を閉ざしたのである。被控訴人は,一般的な建物賃料の下落を主張するが,自己の収受する建物賃料を開示しないのであって,これが下落したとの事実を認めることもできない。したがって,当裁判所としては,上記減額意思表示の時点でも,適正な地代の額は,現在の地代の額を下回っておらず,かえって上回っている可能性も残されていて,これを否定することはできないものと認定判断する。この認定判断を覆すべき証拠はない。
※東京高裁平成14年10月22日
本記事では,継続賃料の算定で用いる4つの手法のすべてを否定した裁判例を紹介しました。
実際には,個別的な事情によっては,法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に地代その他の借地に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。