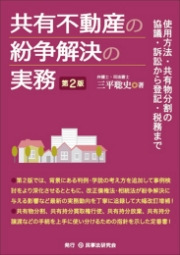【旧借地法における異議のない建物再築による期間延長(基本)】
1 旧借地法における異議のない建物再築による期間延長(基本)
旧借地法が適用されるケースで、借地人が建物を再築し、これに対して地主が異議を述べない場合、契約期間が延長されます。本記事ではこのことを説明します。
2 建物再築に関する新旧法の適用の振り分け(概要)
最初に、旧借地法が適用されるケースとはどのようなものかを押さえておきます。それは、更新契約ではなく、最初の契約が平成4年8月よりも古いものです。
建物再築に関する新旧法の適用の振り分け(概要)
あ 再築の規定の適用
借地借家法の施行前に設定された借地権について
借地法の建物再築による期間の延長の規定が適用される
※改正附則7条
い 借地借家法の施行日
平成4年8月1日
※改正附則1条
※平成4年政令25号
3 状況別の建物再築による結論(まとめ)
旧借地法が適用されるケースで、建物の再築がなされた状況は大きく3つに分けられます。それぞれの結論を最初に整理しておきます。
旧借地法7条は、地主が異議を述べない場合には期間が延長されると規定されています。地主が事前に承諾した場合ももちろん、異議を述べていないので期間の延長は適用されます。
一方、地主が異議を述べた、つまり反対した場合は、期間の延長はありません。では、承諾がない再築は解除できるかというと、そうとは限りません。
再築(増改築)を禁止する特約がなければ違反ではないので解除はできません。増改築禁止特約があれば解除できることもありますが、救済的に解除が否定されることもあります。
状況別の建物再築による結論(まとめ)
あ 地主が承諾したケース
地主の異議がないにあたるので、期間が延長される(法定更新)
実務では、承諾料の支払とともに延長された期間を明記した契約書の調印をすることがよくある
い 地主が異議を述べないケース
期間が延長される(法定更新)
う 地主が異議を述べた(反対した)ケース
ア 増改築禁止特約なしのケース
期間の延長(法定更新)はない
(用法違反にあたらない限り)解除できるわけではない
次回の期間満了の時に更新拒絶が認められる方向に働く
イ 増改築禁止特約があるケース
特約違反による解除が認められることがある
状況によっては、解除が認められないこともある
詳しくはこちら|借地契約の増改築禁止特約の有効性と違反への解除の効力
4 借地法7条の規定の基本
(1)(旧)借地法7条の条文
ここから、借地法7条のルールの中身の説明に入ります。最初に条文を確認しておきます。
(旧)借地法7条の条文
但シ残存期間之ヨリ長キトキハ其ノ期間ニ依ル
※借地法7条
(2)条文の要件と効果の整理
前記の条文を機械的に、要件と効果に整理します。
条文の要件と効果の整理
あ 要件
借地権の消滅前において
建物が滅失した
借地人が残存期間を超えて存続する建物を築造した
地主が遅滞なく異議を述べなかった
い 効果
借地期間が延長される
なお、条文上は「借地権ハ・・・存続ス」と書いてありますが、要するに期間が延長されるということです。当事者が意図していないのに期間の延長の効果が生じるので、法定更新とも呼ばれています。ただ、法定更新というワードは通常、期間満了の場合で使うので、建物再築で使うとまぎらわしいです。
そこで本記事では、混同を避けるため、再築の期間延長について法定更新とは呼ばないことにします。
5 建物の滅失と築造の意味(概要)
条文上、建物の滅失と築造という用語が使われています。要するに建物を再築することです。実際のケースでは、再築(滅失と築造)にあたるかどうかがハッキリしないこともあります。簡単にいえば、工事の規模で判定することになります。修繕工事でも、規模が大きければ再築と同じ扱いになることがあります。
建物の滅失と築造の意味(概要)
あ 「滅失」の意味
「滅失」とは、建物が消滅することである
借地人による取壊しも含む
詳しくはこちら|建物の『滅失』の意味と判断基準(新旧法共通)
い 「築造」の意味
ア 基本
「築造」とは通常「新築(再築)」のことである
イ 大規模修繕→「滅失+築造」扱いの可能性あり
大規模修繕は「滅失+築造(再築)」として扱われることもある
詳しくはこちら|借地上の建物の大規模修繕は再築(滅失・築造)にあたるかどうか
6 建物再築により延長される期間→20年か30年
(1)延長される期間(まとめ)
借地人が建物を再築して、これについて地主の異議がない(承諾した)場合は、期間が延長されますが、この期間は、建物が滅失した日から30年または20年です。新たな建物が堅固建物であれば30年、非堅固建物であれば20年です。
延長される期間(まとめ)
あ 延長される期間の起算点
建物の滅失の日(後記※1)
い 延長される期間の長さ(法定期間)
新たな建物
期間
堅固建物
30年間
非堅固建物
20年間
※借地法7条本文
う 残存期間の短縮否定
元の残存期間の方が法定期間(い)より長い場合
→元の残存期間のままである
=法定期間まで短縮されるわけではない
※借地法7条但書
(2)新たな存続期間の起算点
前記のように、新たな期間の起算点は建物の滅失の時点です。新たな建物の完成時点が妥当だという発想もありますが、明確に判定できることが重視されているのです。
新たな存続期間の起算点(※1)
(前掲東京地判昭45・3・31、星野・借地借家100。なお、最判昭50・9・11民集29・8・1273のような事案では、旧建物が全部取りこわされた時点である)。
起算点としてこの時点がえらばれているのは、起算点を明瞭ならしめる趣旨からである、と説かれている(広瀬98)。
しかし、築造建物の耐用年数を全うさせるという本条の趣旨を貫くには、立法論として、新建物築造着手の日(より理論的には築造完成の日とすべきであろうが、借地人の工事遷延により借地権の存続期間満了が遅れるのは、不都合であろう)を起算点とすべきであるかもしれない(解釈論としてこの見解をとるものとして、水本=遠藤編・前掲書64〔明石〕)。
※鈴木禄弥・生熊長幸稿/幾代通ほか編『新版 注釈民法(15)増補版』有斐閣2010年p452
本記事では、旧借地法において建物再築による期間延長について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に借地上の建物の増改築(再築)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。