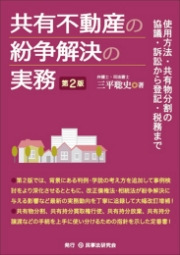【共有者の『容認』による例外的な法定地上権の成立とその判断基準】
1 共有者の「容認」による法定地上権の成立(総論)
法定地上権の成立要件の1つに、抵当権設定時に土地・建物の所有者が同一であった、というものがあります。
この点、土地や建物が共有のケースでは、この要件に該当するかどうかは解釈で決まります。
詳しくはこちら|法定地上権の基本的な成立要件
実際にいろいろなパターンの権利関係のケースにおいて、法定地上権が成立するかどうかの判例があります。
判例の判断の中で、抵当権を設定していない共有者の立場(利益)が大きく影響しています。
判断基準の1つとして、抵当権を設定していない共有者が、法定地上権の成立を「容認」していた場合に、法定地上権を成立させるというものがあります。
この例外的な扱いは、その後の判例で大きく制限されています。
本記事では、このような、共有者の「容認」による例外的な法定地上権の成立と、その判断基準を説明します。
2 昭和29年最判・土地共有持分の競売→法定地上権否定
まず、基本的には、土地の共有持分の競売(抵当権実行)では法定地上権が成立しません。
これが現在でも大原則となっています。
昭和29年最判・土地共有持分の競売→法定地上権否定(※1)
あ 権利関係
建物 A単独所有 抵当権設定なし 土地 A・Bの共有 A持分に抵当権設定
い 抵当権実行
抵当権が実行された
競売により土地・建物の所有者が異なる状態になった
う 法定地上権の成否
他の共有者(B)の権利が制約されるのは不当である
→法定地上権は成立しない
※最判昭和29年12月23日
3 昭和44年最判・「容認」による例外的成立(仮換地ケース)
(1)「容認」による例外(昭和44年最判・概要)
昭和29年最判は法定地上権を一般的に否定しましたが、昭和44年の判例は、これの例外を認めます。
抵当権の設定に関与していない土地共有者が、法定地上権の成立を容認していた場合に限って例外的に法定地上権を肯定するという判断です。
「容認」による例外(昭和44年最判・概要)(※2)
あ 権利関係
建物
A単独所有
抵当権を設定した
土地
A・Bの共有
抵当権設定なし
抵当権が実行された
い 法定地上権の成否(原則)
原則として法定地上権は成立しない(昭和29年(前記※1)判例と同じ)
う 法定地上権の成否(例外)
Bが法定地上権の発生をあらかじめ容認していた場合
→例外的に法定地上権は成立する
え あらかじめ認容する具体例
Bが持分に基づく使用収益を事実上放棄した
BがA(建物所有者である土地共有者)の処分に委ねていた
お 個別事案の判断
Bは法定地上権の発生を容認していたと認定した
→例外的に法定地上権の成立を肯定した
※最判昭和44年11月4日
詳しくはこちら|共有と法定地上権の成否(単独所有への抵当権設定)
(2)昭和44年最判の事案の特殊事情→仮換地
前記の昭和44年最判は、具体的事案をみると非常に特殊な事情があります。
土地は法律上共有であることは間違いないのですが、実質的には土地を分筆して、建物の敷地部分は単独所有であるのと同様の状況だったのです。仮換地の場合には、分筆ができないので、仕方なく共有としておいて、共有者Aが特定の土地(1筆の土地のうち甲部分)を単独で使う(占有する)ということがよくあるのです。
昭和44年最判の判断は、以上のような特殊事情がある事案についての個別的な判断です。一般化した基準を立てたわけではありません。そこで、この理屈がどの範囲であてはまるか、ということは(昭和44年最判では)はっきりしていないのです。
昭和44年最判の事案の特殊事情→仮換地
あ 平成6年最判の判例解説による指摘
・・・昭和四四年判例については、仮換地の一部が売買されたという特殊な事案についての判断であるところ、この事案については、もしもこれが通常の土地についての売買であったとすれば、土地分筆の上で売買契約がなされた後に建物が建築されてこれに抵当権が設定され、したがって法定地上権は問題なく成立したであろうと考えられるにもかかわらず、たまたま仮換地の一部について売買がなされたがゆえに土地が共有のままとなっていた点をとらえて法定地上権の成立を否定することはいかにもバランスを欠く、という面があった。
それに加えて、同判例がいわゆる事例判例であったことから、法定地上権を肯定するために同判例がとった前記の理由付けは、あくまで判示の事実関係の下における事例判断の前提としてのものであった。
そのため、建物所有者以外の土地共有者らの容認という前記の判断基準がどのような事案にまで適用されうるものであるかについては、同判例からは必ずしも明らかではなかった。
※瀬木比呂志稿/『最高裁判所判例解説 民事篇 平成6年度』法曹会1997年p628、629
い 実務の現場の見解
昭和44年最判(前記※2)の事案について
法律上は(従前地の)共有持分であった
実質的には仮換地の特定部分の売買である
特殊な事案に関する判断であるため、一般化することには問題がある
※東京地裁民事執行実務研究会編『改訂 不動産執行の理論と実務(上)』法曹会1999年p266
4 平成6年最判・「容認」の判断基準→主観的要素否定方向
(1)平成6年最判の基本的規範→「容認」基準は高め
昭和44年最判が示した「容認」について、より一般論として判断基準を示した判例が登場しました。それが平成6年最判です。
平成6年最判は、土地が共有であることを前提として、土地共有者の1人だけについて民法388条本文の要件を満たす場合に、原則として法定地上権は成立しない、そして、例外的に法定地上権が成立するのは、法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることができるような特段の事情がある場合である、という大きな判断基準を示しました。
さらに、この「法定地上権の発生を容認していたとみることができる」の中身は、「土地に対する使用収益権を事実上放棄し、他の土地共有者の処分にゆだねていた」というような高いレベルの基準を示しました。
平成6年最判の基本的規範→「容認」基準は高め
あ 判決文引用
共有者は、各自、共有物について所有権と性質を同じくする独立の持分を有しているのであり、かつ、共有地全体に対する地上権は共有者全員の負担となるのであるから、土地共有者の一人だけについて民法三八八条本文により地上権を設定したものとみなすべき事由が生じたとしても、他の共有者らがその持分に基づく土地に対する使用収益権を事実上放棄し、右土地共有者の処分にゆだねていたことなどにより法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることができるような特段の事情がある場合でない限り、共有土地について法定地上権は成立しないといわなければならない(最高裁昭和二六年(オ)第二八五号同二九年一二月二三日第一小法廷判決・民集八巻一二号二二三五頁、最高裁昭和四一年(オ)第五二九号同四四年一一月四日第三小法廷判決・民集二三巻一一号一九六八頁参照)。
※最判平成6年12月20日
い 判例解説
ここで注目すべき点は、本判決が、建物所有者でない土地共有者らの容認を認めることができるための要件について、「他の共有者らがその持分に基づく土地に対する使用収益権を事実上放棄し、右土地共有者の処分にゆだねていたことなどにより法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることができるような特段の事情がある場合」に限られるとして、昭和二九年判例の示した原則に対する例外となるべき場合についてかなり厳格な考え方を示していることである。
前記の容認が認められるためには、単にその意思が表示されているというだけでは足りず、それを裏付ける具体的な事情が必要であるという考え方が、ここで示されているといえよう。
※瀬木比呂志稿/『最高裁判所判例解説 民事篇 平成6年度』法曹会1997年p636
(2)平成6年最判の示した判断要素の範囲とあてはめ
平成6年最判は、前述の判断基準に、事案内容をあてはめる時のルールも示しました。当然ですが、同じ判断基準でも判断材料(判断要素)によって結論が変わります。たとえば、共有者同士の関係が親子や夫婦という事情によって容認していたと読み取れることもありえます。
ところで、法定地上権の成否によって、大きな影響が及ぶのは、土地と建物の所有者(共有者)だけではなく、(後順位を含む)担保権者や一般債権者、入札者(買受人・競落人)ととても幅広いです。
そこで、判断材料は、明確に外部から分かる範囲の情報だけに限定して、判断結果のぶれを防ぐ、という方針が採用されたのです。結論として、判断材料は登記から読み取れる範囲に限られるというルールが示されました。共有者間の関係は登記からは読み取れないので判断材料から除外することになります。
なお、競売手続の際には現況調査報告書などのいわゆる3点セットが公表されますが、これは、競売手続が始まらないと作成も公表もされません。たとえば後順位抵当権者が抵当権を取得した(設定を受けた)時点では3点セットは存在すらしません。3点セットは判断材料には入らないことになります。
平成6年最判の示した判断要素の範囲とあてはめ
あ 主観的要素の影響(前提)
これを本件についてみるのに、原審の認定に係る前示事実関係によれば、本件土地の共有者らは、共同して、本件土地の各持分について被上告人Mを債務者とする抵当権を設定しているのであり、M以外の本件土地の共有者らはMの妻子であるというのであるから、同人らは、法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとも考えられる。
い 判断要素の範囲(規範)
しかしながら、土地共有者間の人的関係のような事情は、登記簿の記載等によって客観的かつ明確に外部に公示されるものではなく、第三者にはうかがい知ることのできないものであるから、法定地上権発生の有無が、他の土地共有者らのみならず、右土地の競落人ら第三者の利害に影響するところが大きいことにかんがみれば、右のような事情の存否によって法定地上権の成否を決することは相当ではない。
う 本件の判断要素の中身
そうすると、本件の客観的事情としては、土地共有者らが共同して本件土地の各持分について本件建物の九名の共有者のうちの一名である被上告人Mを債務者とする抵当権を設定しているという事実に尽きるが、
え 本件のあてはめ(判定)
このような事実のみから被上告人M以外の本件土地の共有者らが法定地上権の発生をあらかじめ容認していたとみることはできない。
けだし、本件のように、九名の建物共有者のうちの一名にすぎない土地共有者の債務を担保するために他の土地共有者らがこれと共同して土地の各持分に抵当権を設定したという場合、なるほど他の土地共有者らは建物所有者らが当該土地を利用することを何らかの形で容認していたといえるとしても、その事実のみから右土地共有者らが法定地上権の発生を容認していたとみるならば、右建物のために許容していた土地利用関係がにわかに地上権という強力な権利に転化することになり、ひいては、右土地の売却価格を著しく低下させることとなるのであって、そのような結果は、自己の持分の価値を十分に維持、活用しようとする土地共有者らの通常の意思に沿わないとみるべきだからである。
お 第三者への影響への配慮
また、右の結果は、第三者、すなわち土地共有者らの持分の有する価値について利害関係を有する一般債権者や後順位抵当権者、あるいは土地の競落人等の期待や予測に反し、ひいては執行手続の法的安定を損なうものであって、許されないといわなければならない。
※最判平成6年12月20日
か 権利関係の要点(補足)
建物 A・他の8人 抵当権設定なし 土地 A・B・Cの共有 全体に抵当権を設定した→実行された
(3)平成6年最判の射程・建物単独所有のケースの検討
平成6年最判が示した前述の判断基準は、土地が共有であることが前提となっています。では、建物が共有のケースと建物が単独所有のケースの両方にあてはまる(射程に含む)のでしょうか。これについて判例解説では、建物が単独所有であるケースは含まないという見解が示されています。建物が単独所有(土地は共有)であるケースでは、法定地上権が成立する、しない、という両方の判断があり得る(確定的な判断はできない)ということです。
平成6年最判の射程・建物単独所有のケースの検討
あ 判例解説・メイン部分
本件は、・・・建物の単独所有者の債務を担保するために土地全体に抵当権が設定された場合とは事案を異にしており・・・
本判決は「・・・本件の客観的事情としては、土地共有者らが共同して本件土地の各持分について本件建物の九名の共有者のうちの一名であるY1を債務者とする抵当権を設定しているという事実に尽きる・・・」と注意深く説示しているのであって、本判決の射程距離が建物が単独所有である前記のような場合に及ばないことは明らかといえる。
そして、本判決が示した「容認」についての前記のような枠組を前提にしたとしても、右のような場合の法定地上権の成否については、なお、肯定、否定いずれの考え方も成り立ちうるところと思われる。
右のような事案についての最高裁判所の判断を本判決から軽軽に予測することは慎まなければならないであろう(注一〇)。
※瀬木比呂志稿/『最高裁判所判例解説 民事篇 平成6年度』法曹会1997年p638
い 判例解説・注記
ア 両説の可能性
(注一〇)なお、右のような場合(建物が甲の単独所有、土地が甲乙の共有で、甲の債務を担保するために、甲乙が共同してその各土地持分に抵当権を設定した場合)については、前記2(三)の(3)で述べたとおり、両様の考え方が成り立ちうるものであり、いずれの考え方にもそれなりの根拠があると思われるのであるが、仮にこの点について肯定説をとった場合に生じうるいくつかの問題点について、簡単にふれておきたい。
イ 後順位抵当権への配慮
第一は、右の設例で乙の持分について乙自身が自己の債務を担保するために後順位で抵当権を設定していた場合でも乙の容認を肯定しうるかという点である。
第二は、土地の全部でなく、甲か乙の持分のみが競売されるに至った場合はどうかという点である。
第三は、抵当権の被担保債務の金額が土地価格に比べて著しく小さい場合はどうかという点である。
まず、第一の場合については、肯定説を前提としても、この場合には、乙はその持分の担保価値を自己のためにも用いているのであるから、自己の持分に基づく土地に対する使用収益権を事実上放棄し、甲の処分にゆだねていたとはみ難く、したがって乙の容認を認めるべきではない反対事情が存在する場合として、法定地上権の成立は否定されるのではないかという問題がある(なお、後記の千種秀夫裁判官の補足意見は、その六において、この問題に言及して、前記のような場合についての法定地上権の成否について積極の結論を導くことが容易ではないことの一つの論拠としているが、右補足意見は、同時に、本件においてはY1が九名の建物共有者のうちの一名にすぎないという事情も考慮されなければならない旨述べており、全体の文脈からみれば、補足意見中の右の記述が建物の単独所有者の債務を担保するために土地全体に抵当権が設定された場合についてまで否定説をとることを前提としているとみることは、必ずしも相当でないと思われる。)。
なお、甲の債務を担保するための抵当権設定後に乙の持分のみについてその債権者から差押えがされている場合についても、同じような問題がある。
ウ 甲持分のみの競売→肯定
次に、第二の場合については、甲の持分のみが競売されるときには、土地全体が競売される場合と同様に法定地上権の成立を肯定してよいと思われる。
エ 乙持分のみの競売→否定
乙の持分のみが競売されるときについては、前記のとおり、甲の乙に対する土地利用権(利用関係)が競落人との関係でも引き継がれるにすぎず、法定地上権は成立しないと考えられる(東京地裁民事執行実務研究会・前掲二六六頁)。
オ 被担保債務金額が僅少のケース→容認否定方向
最後に、第三の場合については、抵当権の被担保債務の金額が土地価格に比べて著しく小さい場合には、肯定説を前提としても、乙の容認を認め難いこともありうるのではないかと思われる。
もっとも、そのような事案について抵当権が実行されるまでに至ることは、実際上はまれであろう。
※瀬木比呂志稿/『最高裁判所判例解説 民事篇 平成6年度』法曹会1997年p640、641
5 抵当権実行と民事執行法上の競売の違い(容認判定への影響)
以上のように、(一定の状況では)法定地上権の成否の判断は、共有者が法定地上権の成立を容認していたと評価できるかどうか、で決まります。以上の説明では、抵当権の実行のケースを前提としていました。
この点、民事執行法による差押、競売でも、法定地上権が成立することがあります。根拠は民法388条ではなく民事執行法81条です。この場合には、過去に抵当権を設定するという行為がないので、あらかじめ容認していたかどうか、という判定は(抵当権の実行よりは)否定方向に傾くことになります。
抵当権実行と民事執行法上の競売の違い(容認判定への影響)
※瀬木比呂志稿/『最高裁判所判例解説 民事篇 平成6年度』法曹会1997年p626、627
6 形式的競売における法定地上権否定事例
平成6年最判の後に、この基準を適用して法定地上権を否定した裁判例があります。
ただし、担保権の実行ではなく形式的競売であることも、法定地上権を否定する理由として明言しています。
いずれにしても、『容認』を否定することが明確に示されているので、参考となる事例として紹介します。
形式的競売における法定地上権否定事例
あ 権利関係
建物
A単独所有
抵当権設定なし
土地
A〜Eの5人の共有
A持分に抵当権を設定した
土地について換価分割による形式的競売が行われた
土地・建物の所有者が異なる状態になった
い 法定地上権の判断基準時点
法定地上権の成否は先行する抵当権を基準として判断する
詳しくはこちら|実行していない先行抵当権を基準として法定地上権の成否を判断する
う 『容認』理論の適用(前提)
形式的競売であっても『容認』により法定地上権の成立を認める可能性はある
え 法定地上権の成否
抵当権設定時点において
Aは土地の共有者でありかつ建物所有者であった
B〜Eが『法定地上権の発生をあらかじめ容認していた』場合
→法定地上権が成立する(前記※2)
お 裁判所による『容認』の判断
『容認していた』とみることはできない
か 補足説明
法定地上権を否定する理由として
形式的競売であることも示している
詳しくはこちら|形式的競売における法定地上権の適用の有無
※福岡高裁平成19年3月27日(形式的競売について)
7 関連テーマ
(1)土地共有者の合意による利用権原(概要)
ところで、以上のように、土地AB共有、建物A単独所有、というケースは、土地の共有者が土地(共有物)を使用している状態です。土地の占有権原は共有者ABの合意またはAの共有持分権ということになります。いずれにしても共有であることが前提の占有権原です。
この利用権原を対抗できるのは、土地の共有者(B)と、BからBの持分を取得した者です(民法254条)。土地全体の競売で買受人Cが土地の所有権を取得したケースでは、共有ではなくなったのでBの土地占有権原をCに対抗できません。このことは別の記事で(担保権実行ケースについて)説明しています。
詳しくはこちら|担保権実行における土地共有者が合意した利用権の消滅か存続
本記事では、競売の対象不動産の共有者の「容認」によって法定地上権の成立を認める理論(解釈)について説明しました。
実際には個別的な事情により結果が違ってくることもあります。
実際に不動産の競売に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。