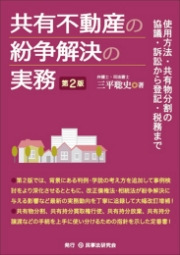【共有不動産に関する不正な登記の是正方法の従来方式判別基準】
1 不正な登記の抹消を認める範囲(全部抹消の可否)の従来方式の判別基準
実体上の権利と合致しない登記は無効です。そこで、一定の関係者は登記の是正を請求することができます。具体的には、不正な登記の抹消登記や更正登記手続、あるいは真正な登記名義の回復による移転登記手続の請求です。
このような登記手続の請求が、共有が関係する不動産で行われる場合、誰が請求できるか(原告となれるのか)、どのような登記(抹消登記、更正登記、移転登記)を請求できるのか、また、更正登記の場合には原告の持分を回復する範囲を超えた是正を請求できるか、という問題があります。
詳しくはこちら|共有不動産の不正な登記の是正の全体像(法的問題点の整理・判例の分類方法・処分権主義)
これについては、大きく2つの考え方があります。そのうち、従来からあった見解(従来方式の判断基準)を本記事では説明します。
2 請求を認める範囲による判例の分類(従来方式=甲・乙類型)
請求を認める範囲についての従来方式の判別基準は、登記上侵害している者(被告)が第三者(共有者以外)か共有者であるかで区別するというものです(後記)。
侵害者が第三者であるケースを甲類型と呼び、この場合は原告の持分の回復を超える抹消を認めます。
侵害者が共有者であるケースを乙類型と呼び、この場合は原告の持分の回復を超える抹消を認めません。
実際に請求を認める範囲を示した判例は数多くあります。
詳しくはこちら|第三者(共有者以外)の不正な登記の抹消請求の判例の集約
詳しくはこちら|共有者の不正な登記の抹消請求の判例・裁判例の集約
以上の多くの判例を従来方式の分類(甲類型・乙類型)で振り分けてみましょう。
請求を認める範囲による判例の分類(従来方式=甲・乙類型)
| ↓被告の状態 | 原告の持分回復の範囲に限定した是正を認める(全部抹消NG) | 原告の持分回復を超えた是正を認める(全部抹消OK) |
| 実体上の権利なし(第三者・甲類型) | 平成22年最高裁(※2) | 大正12年大判・(大正15年大判)・昭和31年最高裁・昭和33年最高裁・昭和35年最高裁・平成15年最高裁(※3) |
| 実体上の権利あり(共有者・乙類型) | 大正10年大判・昭和37年最高裁・昭和38年最高裁・昭和39年1月最高裁・昭和39年4月最高裁・(昭和43年大阪高裁(※5))・昭和44年最高裁・昭和59年最高裁・昭和60年最高裁 | (大正8年大判(判例変更前))・平成8年東京高裁・平成17年最高裁(※4) |
い 注記
昭和43年大阪高裁(前記※5)は、他の判例とは異なる判断がなされている、その理由については別の記事で説明している
詳しくはこちら|原告の持分回復を超える更正登記を認めた昭和43年大阪高裁の分析
この判例の分類の表を踏まえて、以下各類型の内容を説明します。
3 第三者に対する全部抹消の認容(甲類型)
第三者に対する抹消請求(甲類型)では、原則的に原告の持分の回復を超えた抹消を認める結果となっています。
平成22年最高裁だけが、この判別に反していることになります。
第三者に対する全部抹消の認容(甲類型)
あ 前提事情(甲類型の内容)
実体のないA名義の所有権(共有持分)登記がある
Aは所有権・共有持分を持たない
=共有者ではない
=第三者である
い 原告の持分を超える抹消請求(原則=肯定)
共有者の1人が自己の共有持分を超えて実体に合致しない登記の抹消を請求することを認める
多くの判例がこれに該当する
う 原告の持分を超える抹消請求(例外=否定)
平成22年最高裁(前記※2)は
原告の持分を超える抹消請求(い)を否定している
原告の共有持分の範囲に限り一部抹消(更正)登記手続を認めている
え 原告の持分を超える抹消請求(侵害なしの原告)
平成15年最高裁(前記※3)は
原告が登記上侵害を受けていない(登記に正確に記載されている)ケースについて
不正な持分登記の抹消を求めることを認めている
原告の持分を超える抹消請求を認めるという意味では『い』に含まれる
(別に原告となれるかどうかとしての問題は生じる)
詳しくはこちら|不正な登記の抹消請求における共同訴訟形態・原告になれる共有者の問題
※『最高裁判所判例解説 民事篇 平成15年度(下)』法曹会2006年p396参照
4 共有者間の一部抹消のみの認容(乙類型)
共有者が他の共有者に対して不正な登記の抹消を請求するというのが乙類型です。この場合には原則的に原告の持分の回復を超える抹消を認めないことになります。つまり、全部抹消は否定され、一部抹消(更正登記)だけが認められるという意味です。
前記の判例の分類の表では、大部分がこれに該当します。これに該当しない(裁)判例は3つあります。それぞれのケースには特殊性があります。そのうち2つのケースの特殊性は、手続的に更正登記(一部抹消)をしたくてもできないというものです。
共有者間の一部抹消のみの認容(乙類型)
あ 前提事情(乙類型の内容)
A名義の所有権or共有持分の登記がある
Aは共有持分権を有している
=まったくの無権利者ではない
しかし登記の方が実体を超過している
=登記と実体は一部合致している
い 原告の持分を超える抹消請求(原則=否定)
共有者の1人が自己の共有持分を超えて実体に合致しない登記の抹消を請求することを認めない
原告の共有持分の範囲に限り一部抹消(更正)登記手続を認める
多くの判例がこれに該当する
う 原告の持分を超える抹消請求(例外=肯定)
特殊な事情(え)がある場合、『い』の例外として、原告の持分を超える抹消請求(全部抹消)を認める
え 例外となる特殊事情の内容
ア 大正8年11月大判(前記※4)
実体は家督相続が適用されず共同相続となった
家督相続(単独承継)の登記がなされた
→登記全体が無効となった(全部抹消が認められた)
イ 平成17年最高裁(前記※4)
数次相続による中間省略登記のうち
第1次の相続の内容が(一部)実体に合致していなかった
→登記の同一性を欠くため、更正登記(一部抹消)ができない
ウ 平成8年東京高裁(前記※4)
実体のない生前贈与と相続による持分取得の重複がある
しかし、登記された登記原因(贈与)が実体(相続)と異なっていた
→登記の同一性を欠くため、更正登記(一部抹消)ができない
5 平成15年最高裁と従来の分類の整合性の考察
ところで、前記の判例のうち、平成15年最高裁は原告となれる共有者についての判断として特徴があります。
一方、本記事のテーマである請求を認める範囲については、甲類型の1つとして原則どおりに全部抹消を認めたものなので、特に変わっているわけではありません。
これに関して、共有者間の抹消請求なのだから乙類型であるという前提で、原則的な扱い(原告が受けている侵害の範囲内で抹消を認める)とは異なるという指摘もあります。この見解は、遺産という特殊性を理由に例外的な扱いがなされたと説明します。
ところで平成15年判例は、抹消登記請求を認める根拠として、保存行為を使わず、共有持分権の性質(そのもの)を使っています。共有持分権の性質により、共有者の1人が共有物の妨害排除を請求できることは、甲分類も乙分類も変わりません。つまり、平成15年判例の判断により、従来方式の判断基準には無理があることが表面化したともいえます。
平成15年最高裁と従来の分類の整合性の考察
あ 乙類型との不整合
平成15年最高裁の事案において
原告は自己の持分は登記上侵害されていない
従来方式の共有者間の抹消請求(乙類型)だとすると全部抹消は認められないはずである
い 整合性・考察
遺産という特殊性がある
他人名義の持分登記は遺産分割の支障になる
持分権の行使に支障がある(後記『う』)ことから持分権の侵害を認めることも考えられる
担保価値維持保存義務とは異なるが、債権者代位権の転用による処理も考えられよう
※能見善久ほか編『論点体系 判例民法2物権 第3版』第一法規2019年p358
う 遺産の共有登記の法的意味
共有物分割では登記された共有者が当事者となる
詳しくはこちら|共有物分割(訴訟)の当事者(共同訴訟形態)と持分割合の特定
遺産分割ではこれと異なり登記上の共有者で判断できない
→不実の登記があると他の相続人(共有者)としては誰を遺産分割協議の相手方とするのかが不明確となる
また、共有を解消する手続の種類は、遺産分割、共有物分割のいずれか、という選択も不明確となる
詳しくはこちら|遺産共有の法的性質(遺産共有と物権共有の比較)
→現実に他の共有者が困ることになる
え 甲類型との整合性
平成15年最高裁の事案は、共有持分譲渡が無効であるという前提では
被告は共有者の1人ではないことになる
→従来方式の甲類型に該当する
→従来方式の理論からは全部抹消を認めることになる
平成15年最高裁の判断結果と整合する
※『最高裁判所判例解説 民事篇 平成15年度(下)』法曹会2006年p395
お 請求の根拠(参考)
平成15年判例は、共有者1人による抹消登記請求を認める根拠として保存行為を使わず、共有持分権の性質(そのもの)を使っている
詳しくはこちら|不正な登記について原告の持分を超える抹消を認める根拠(保存行為・共有持分権)
甲類型・乙類型のどちらでも、原則として共有者の1人が妨害排除請求権を行使することができるはずである
平成15年判例の理論により、従来方式(甲類型・乙類型の区別)の説明に無理が出てくることが表面化したといえる
6 平成15年最高裁のアレンジ(不実の持分移転登記)
平成15年最高裁の事例を乙分類とする前記の見解は、さらに事案内容を少し変えて考察しています。原告への更正登記が可能である状態を想定した上で、この場合には結論は違って(原則に戻って)登記上原告が侵害された範囲に限って抹消請求が認められることになるはずだと指摘しているのです。
平成15年最高裁のアレンジ(不実の持分移転登記)
あ 主要事項の整理
| 原告 | 被害者の一部 |
| 被告 | 実体上の権利あり(共有持分権) |
| 不正な登記 | 共有持分移転登記(結果的に単独所有となった) |
| 更正登記の可否 | 原告への更正登記は可能 |
| 判断(想定) | 全部抹消NG(原告の被侵害部分のみ) |
い 事案
相続人はA・B・Cであった
法定相続による登記(A・B・Cの共有)をした
その後、Cが分割協議書を偽造してA・Bの持分についてCへの移転登記をした
=『A→C』『B→C』の2件の登記(申請)である
この時点で登記上はCの単独所有となった
AがCに対して抹消登記手続を請求した
う 法的判断
Aの持分の移転登記(『A→C』)の抹消登記手続しか請求できない
B(原告ではない)の持分の移転登記の抹消登記手続を認めると私的自治への干渉となる
※能見善久ほか編『論点体系 判例民法2物権 第3版』第一法規2019年p361、362
実は、この考え方は、新方式の考え方そのものといえます(後述)。
7 従来方式判別基準の不合理性
従来方式判別基準は、以上のように、甲類型か乙類型かによって違う結論を採用します。その理由の要点は、甲類型の場合は妨害排除の実現を優先し、乙類型の場合は処分権を優先する、というようなものです。
これについて、甲類型・乙類型のいずれも、登記に不実部分があることは変わらないので、2つの類型で是正の範囲に差異を設けることは合理性を欠くし、乙類型の判例は「被告が共有者である」ことを理由として抹消の範囲を制限しているとは理解できない、という指摘がなされています。
従来方式判別基準の不合理性
あ 判例解説
・・・被告が共有者の1人であるかどうかによって、原告が自己の持分を超える部分について登記の抹消を求めることができるかどうかが変わるのかという点が問題になる。
被告が共有者の1人であったとしても、被告の共有持分権を超える持分の登記を有している場合には、超過部分については被告は他の共有者の権利を侵害していることに変わりがないはずである・・・。
それなのに、この場合には、不実の登記がされている侵害部分であっても、原告の持分を超える部分については、抹消を請求することができなくなるというべきであろうか。
そのような考えには、合理性を見いだし難いし、乙類型の判例もそのような趣旨をいうものと理解するのは相当でない。
※尾島明稿/『最高裁判所判例解説 民事篇 平成15年度』法曹会2006年p394
い 最新裁判実務大系
被告が第三者か共有者かで判別する仮説について
→不合理である
※滝澤孝臣編著『最新裁判実務大系 第4巻 不動産関係訴訟』青林書院2016年p372
8 新方式の判別基準(概要)
以上のように、従来方式の判断基準を使うと、うまく分類できる判例が多くありますが、当てはまらない判例も多く生じます。そのため、例外となる理由、つまり個別的な特殊事情を探し出す必要が出てきます。従来方式の判別基準は無理が出てくるのです。また、そもそも甲類型とでも乙類型で違いを設ける合理的な理由がないともいえます。
この点、結論の違いは、原告への更正登記手続が可能かどうかで説明できます。このように、登記手続の内容を中心に、判別するという新方式が提唱されています。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|共有不動産に関する不正な登記の是正方法の新方式判別基準
本記事では、不正な登記の抹消を認める範囲の判別基準のうち、従来からある考え方を説明しました。
理論は複雑で、いろいろな見解があります。
実際に不正な登記に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。