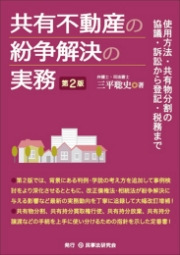【10年の取得時効期間の要件である『無過失』の判断(判断基準と典型例)】
1 10年の取得時効期間の要件である『無過失』の判断
2 取得時効における『過失』の判断基準
3 過失ありと判断された実例(集約)
4 相続した土地の範囲の誤解→過失あり
5 過失なしと判断された実例
1 10年の取得時効期間の要件である『無過失』の判断
所有権の取得時効の時効期間は10年と20年の2種類があります。10年の時効期間が適用されるには,所有物であると信じたことについて善意かつ無過失である必要があります。
詳しくはこちら|取得時効の基本(10年と20年時効期間・占有継続の推定)
本記事では,この『(無)過失』の判断基準や典型的な状況についての判定を説明します。
なお,自己の所有物であると信じたことについて過失があっても(さらに自己の所有物ではないと知っていた場合でも)取得時効が適用されないわけではありません。誤解しやすいのでご注意ください。
2 取得時効における『過失』の判断基準
『過失』を易しい言葉に変えると,注意義務違反となります。要するに平均的な注意をすれば見抜けるはずだった(のに見抜けなかった)ということになります。逆に,平均的な注意では見抜けなかった状況のことが,無過失ということになるのです。
<取得時効における『過失』の判断基準>
あ 『過失』の位置づけ(前提)
自己の所有物であると信じたことについて
占有開始の時点において,善意かつ無過失である場合
→10年の時効期間が適用される
※民法162条2項
詳しくはこちら|取得時効の基本(10年と20年時効期間・占有継続の推定)
い 『過失』の判断基準
民法162条の『過失』について
相当の注意をすれば権原の瑕疵を発見することができるのにもかかわらず,注意の不足によってこれを発見することができなかったことを意味する
※大判大正2年6月16日
3 過失ありと判断された実例(集約)
前記のように,平均的な注意で見抜けたかどうかによって,時効期間が10年なのか20年なのかが決まります。これだけで個々の事案をはっきりと判別できません。
そこで以下,典型的な具体例を挙げて説明します。
まず,自己の所有物であると信じたことについて過失ありと判断された事例をまとめます。
なお,過失ありと判断された結果として,時効期間は20年が適用されます。取得時効が適用されないわけではありません(前記)。
<過失ありと判断された実例(集約)>
あ 登記の調査なし
登記簿を調査しなかった者について
→(自己の所有物であると信じたことについて)過失ありと判断した
※大判大正5年3月2日
い 税務署の図面調査なし
売主が買主に『この溝川が境界だ』と説明した
買主は所轄税務署の図面を見なかった
→過失ありと判断した
※大判昭和17年2月20日
う 法定代理権の調査なし
取引の相手方の法定代理権の根拠(瑕疵の有無)を調査しなかった
→過失ありと判断した
※大判大正2年7月2日
え 行為能力の制限の調査なし
準禁治産宣告(現在の保佐開始の審判)の有無の調査をしなかった
→過失ありと判断した
※大判大正10年12月9日
4 相続した土地の範囲の誤解→過失あり
土地の相続において,相続人が相続財産としての土地の範囲を誤解していたケースがあります。
通常であれば,法務局に保管されている登記情報(登記簿)や公図や地積測量図などによって土地の範囲は特定(現地に再現・復元)できるはずです。そこで,このような調査をしなかったために誤解が生じたということになります。裁判所は過失ありと判断しました。
この点,例えば土地の境界(筆界)が確定していないこともよくあります。そのような場合は,法務局にある登記情報や図面から境界を特定することができません。このような事情があれば,相続した土地の範囲について誤解があっても過失なしと評価される可能性も出てきます。
<相続した土地の範囲の誤解→過失あり>
あ 誤解の内容
相続人が,登記簿に基づいて実地に調査すれば,相続により取得した土地の範囲が甲土地を含まないことを容易に知ることができた
しかし,相続人はこの調査をしなかったために,『甲土地が相続した土地に含まれ,自己の所有に属する』と信じて占有を始めた
い 過失の有無の判断
特別の事情のない限り,相続人は占有の始めにおいて無過失ではない
※最高裁昭和43年3月1日
5 過失なしと判断された実例
過失なしと判断された実例もまとめます。
最高裁判例として,家督相続の制度に関する事情の誤解について,過失なしと判断したものがあります。現在,これと同じようなケースが生じることはほとんどないでしょう。
また,多人数の親族が家業や財産を承継する者を話し合って選んだというケースがあります。法律上は,親族(などの関係者)が誰を相続人にするかを決めることはできません。複数の相続人のうち誰が相続財産を承継するかを決める(遺産分割協議)とは異なります。
法的には相続人を決めたとしても無効です。しかし,相続人として選ばれた者は,自己が所有者になったと信じていました。裁判所は,所有者であると信じたことについて過失はないと判断しました。
<過失なしと判断された実例>
あ 家督相続の制度における財産留保の調査なし
隠居者が確定日付ある証書により財産留保をしなかった
家督相続人において建物の所有権を相続した
隠居者は,有効に留保できたと信じた
→自己の所有物であると信じたことについて過失はないと判断した
※最高裁昭和29年12月24日
い 親族による相続人の選定
空襲により一家が全滅した
本家の再興のため,親族の協議によりA(22歳の女性)が相続人に選ばれた
Aは本家の家業を継ぎ,相続財産に属する土地を占有している
→自己の所有物であると信じたことについて過失はないと判断した
※最高裁昭和35年9月2日
本記事では,10年の時効期間が適用される要件である『(無)過失』の判断基準や典型的状況についての判定を説明しました。
実際には,細かい事情や主張・立証のやり方次第で結論は違ってきます。
実際に取得時効に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。