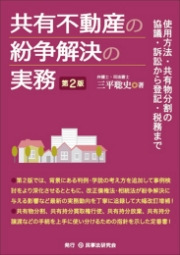【固有必要的共同訴訟における当事者の欠落(訴え漏らし)の治癒】
1 固有必要的共同訴訟における当事者の欠落(訴え漏らし)の治癒
共同訴訟にすることが法律上強制され、合一確定しなければならない訴訟形態のことを固有必要的共同訴訟といいます。つまり固有必要的共同訴訟では本来当事者となるべき者が全員訴訟の当事者(原告か被告)に含まれている必要があります。
詳しくはこちら|共同訴訟形態の基本(通常・固有必要的・類似必要的の分類など)
この点、一部の者が訴訟の当事者から欠落していた場合には、この瑕疵を治癒する(救済する=適法にする)いくつかの方法があります。本記事では、固有必要的共同訴訟における当事者の欠落を治癒する方法について説明します。
2 当事者の欠落の治癒の方法(全体)
当事者の欠落を治癒する方法は、欠落した者による共同訴訟参加と、原告による、別訴を提起した上で弁論の併合を要請する、という2つがあります。別訴提起の代わりに訴えの主観的追加的併合で済ますという方法もアイデアとしてはありますが、実務では否定的です(後記※1)。
当事者の欠落の治癒の方法(全体)
あ 新堂幸司氏見解
固有必要的共同訴訟の共同訴訟人として本来当事者となるべき者が誤って除外されて提起された訴えでも、共同訴訟参加(52条。・・・)、訴えの主観的追加的併合、または別訴を提起して弁論を併合する方法によって当事者となれば、その瑕疵が治癒される。
※新堂幸司著『新民事訴訟法 第6版』弘文堂2019年p788
い 塩崎勤氏指摘
ア 多数説→参加と別訴提起+併合
先ず、必要的共同訴訟(注・固有必要的共同訴訟を意味すると思われる)の場合には、共同して当事者となるべき者が訴訟を共同にすることが適法要件であるが、訴提起時に一部の者が欠けていたとしても、欠けていた者が、後日民訴七五条の共同訴訟的参加をして、その訴訟に加わるか、あるいは一部の者から別訴の提起があったため当事者となり、裁判所が民訴一三二条に則りこの別訴を前記の不適法な訴に併合するときは、この当事者適格の欠缺が補正され適法なものになるとして、これを積極に解する説が多数である。
イ 別の見解→参加はNG
他方、民訴七五条は数人が各自適法に独立に訴えまたは訴えられる場合に、独立に訴を提起する代りに、既に行われている他人間の訴訟の判決の効力を受ける以上(同時に訴えられればいわゆる類似必要的共同訴訟の関係に立つ場合)、自ら進んでその訴訟手続を利用して併合審理を求める手段を与えたものであるから、固有必要的共同訴訟における当事者適格の欠缺を補正するために民訴七五条の参加を利用することは許されず、むしろ、共同訴訟の要件を具備する場合は、同時に提起しなくとも、第一審の口頭弁論終結前は一般に共同訴訟人となれる者からまたはかかる者に対し、訴を追加的に併合することによって、当事者の一部を遺脱した場合の不適法の補正を認めるべきだとする説がある。
ウ 判例→参加と別訴提起+併合
判例は、古くから、民訴七五条の共同訴訟参加により、または同一三二条の弁論の併合によって、当事者適格の欠缺の補正が許されるとする態度をとっているといえる。
※塩崎勤稿『共有者の一部が提起した土地境界確定訴訟の控訴審における残余の共有者の共同訴訟参加の可否と控訴審の実体判断の許否』/『判例タイムズ374号』1979年3月p55〜
3 第三者(欠落している者)からの共同訴訟参加→可能
まず、本来当事者となるはずなのに欠落している者(第三者)が、共同訴訟参加することは可能です。判例、学説ともに認めています。第2審以降でも認められる傾向があります。
第三者(欠落している者)からの共同訴訟参加→可能
※大判大正9年7月31日
※岐阜地判昭和28年8月21日
4 別訴(新訴)提起+弁論併合による治癒→可能
実際には、欠落した者A(第三者)が何もしてくれないので、原告サイドでAを当事者に含めるアクションが必要、というのが通常です。その方法は前述のように、別途、新たな訴訟として申立をした上で、その別訴を従来の訴訟に併合するというものになります。
一応、この方法を否定する学説もありますが、多くの学説、判例、実務ともにこの方法を認めています。
別訴(新訴)提起+弁論併合による治癒→可能
あ コンメンタール民事訴訟法
・・・固有必要的共同訴訟の場合に、当初全員を当事者としない瑕疵があっても、脱漏した当事者に対して別訴を提起し、これと前訴とを併合することによって、訴えを適法とすることができる(大判大正12・12・17民集2巻684頁、法律実務(3)291頁、注解(3)436頁〔斎藤=遠藤=小室〕)。
※秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅲ 第2版』日本評論社2018年p350
い 注解民事訴訟法
ア 訴訟要件の判断の基準時→口頭弁論終結時(前提)
必要的共同訴訟の要件は、最終口頭弁論のときを基準とすべきであるから(大審判大正12・12・17民集2巻684頁、同大正13·11·20民集3巻515頁)、そのときに全員が原告または被告となっていればよい。
イ 反対説の紹介(参考)
必要的共同訴訟人となるべき者が、別々に訴えを提起している場合には、裁判所の弁論の併合(132)によっては適法とならないとする見解があるが、共同提起が要件ではないから適法と解すべきである(同旨、菊井=村松・全訂民訴I329頁、細野・要義Ⅱ144頁、三ヶ月・民訴217頁。反対、小山「必要的共同訴訟」民訴講座Ⅰ265頁。なお、判例は弁論併合を認める、・・・)。
ウ 執筆者見解→別訴提起+弁論併合は可能
固有必要的共同訴訟にあっては、脱落していた共同訴訟人となるべきものから、またはこれに対して新訴を提起して、弁論の併合を求めるか、または、75条による共同訴訟参加をすることができる。
これにより当事者適格の欠缺は補正されることになるが、その補正の効果は、訴えの提起のときに遡るのか、その併合提起または参加のときからと解すべきかについては異論がある。
すでに共同訴訟人となるべきものが訴えを提起しているのであるから、補正の効果を遡及させ紛争の実体的解決をはからせるのが妥当であろう。
そうでないと1人の脱落者のため、時効中断・期間遵守ができなくなることがあるからである。
※斎藤秀夫ほか編著『注解民事訴訟法(2)第2版』第一法規出版1991年p185、186
う 全訂民事訴訟法→別訴提起+弁論併合は可能
固有必要的共同訴訟において、全員が訴えまたは訴えられる必要があるといっても、それは訴提起の要件ではない。
したがって、訴提起後に、共同訴訟参加をして、その訴訟に加わる(七五条前註1参照)か、または、別訴の提起があったため当事者となり裁判所がこの別訴を前記の訴に併合し(一三二条。大判大正一二・一二・一七民集二巻六八四頁、細野・要義(一四四頁、三ヶ月・民訴法二一七頁、斎藤・注解(14)一六三頁、反対―小山・前掲民訴講座(一)二六八頁、山田正三・判例批評民訴法(六八事件五五四頁参照)、その結果、口頭弁論終結の時に全員が原告または被告となっておればよい(兼子・条解新版一六九頁、斎藤・注解(24)一六三頁、大判大正一二・一二・一七民集二巻六八四頁、同大正一三・一一・二〇民集三巻五一六頁、同昭和九・七・三一民集一三巻一四三八頁)。
※菊井維大ほか著『全訂 民事訴訟法Ⅰ 補訂版』日本評論社1993年p374、375
え 実務の扱い→別訴提起+弁論併合は可能
(注・固有必要的共同訴訟に限らない一般論として、原告によるアクションとしては)
裁判実務においては、脱落した者を被告として別訴を提起し、法一三二条により弁論を併合しているのが通例であるところ(右田堯雄・民訴法四二五頁)、・・・
※中田昭孝稿『いわゆる訴えの主観的追加的併合の許否』/『最高裁判所判例解説 民事篇 昭和62年度』法曹会1990年p530
なお、ここでの説明の中に登場する大正12年大判は、訴え漏らしではなく、訴訟中に係争物の譲渡によって当事者が変わったという事案です。
詳しくはこちら|共有物分割訴訟の当事者(共同訴訟形態・持分移転の際の手続)
5 弁論の併合の判断の内容
前述の、新訴提起と弁論の併合という方法のうち、弁論の併合(民事訴訟法152条)については、一般論としては裁判所の職権により行います。弁論の併合をするかどうかの判断については裁判所の裁量によります。この点、固有必要的共同訴訟の訴え漏らしの治癒については、併合するのがほぼ必須といえます。具体的には、併合しない場合には裁量の逸脱、つまり違法となる傾向が強いのです。
弁論の併合の判断の内容
あ 加藤新太郎氏論文
ア 原則=裁量
弁論の併合は、後記(3)で述べる場合を除いて、裁判所の手続裁量に委ねられる。
イ 例外=裁量の逸脱
・・・第3に、弁論の併合を認めないことが解釈上裁判所の著しい裁量の逸脱として違法となる場合がある。
・・・第3は、当事者が併合審理を求める正当な利益を有しており、そのような手続保障が要請されている場合に、併合の申立てを認めないことが著しい裁量の逸脱と評価されるケースがこれに当たる。
ウ 固有必要的共同訴訟の訴え漏らしの治癒
(ii)固有必要的共同訴訟において前訴の当事者適格欠缺の違法を補正するため別訴を提起したうえで、弁論併合申請がされた場合などがこれである
エ 裁判例・学説の紹介
固有必要的共同訴訟の場合、共同訴訟当事者の一部を欠いて訴えが提起されても、欠落した当事者に対して提起された別訴を前訴と併合すれば、当事者適格の欠缺の補正が認められ訴えを適法とすることができる(大判大12・12・17民集2巻684頁)。
これについては、
①本来不適法な訴えを裁判所が適法にすることになるから許されないとする説(小山昇「必要的共同訴訟」民訴講座(1)268頁)もあるが、
②当事者適格は本案判決の要件ではあるが起訴要件ではないとして判例を支持する説(法律実務(3)291頁、菊井=村松I754頁、斎藤ほか編(3)436頁、三ヶ月・全集217頁)が多数説であり、さらに、
③かかる場合には、裁判所は弁論を併合するか否かの裁量権を有さず、併合しなければ違法となる(原告は、この場合弁論併合の申立権を有する)とする説(瀧川・前掲実務ノート(2)143頁注(25))もみられる。
このように訴訟要件(当事者適格)欠缺治癒の方法として弁論の併合を利用することは、本来の用法ではなく、いわば便法であるが、訴訟経済上有益であるから、これを否定する理由はないであろう。
むしろ、そうすることが手続的合理性を有し合目的的であるといえるから、手続裁量論の立場からは基本的に、②説ないし③説が相当というべきである。
しかし、③説のように当事者に弁論併合の申立権を認めるという必要はなく、併合をしないことが著しい手続裁量の逸脱(・手続の違法)という評価が加えられるとみれば足りるであろう。
※加藤新太郎稿/竹下守夫ほか編『注釈民事訴訟法(3)』有斐閣1993年p199、201、202、204
い 伊藤眞氏・民事訴訟法
ア 弁論併合の裁量の内容(前提)
(注・固有必要的共同訴訟に限らず)
・・・第三者に対する新訴の提起、および弁論の併合の方式によって主観的追加的併合を認める余地はあるが、従来の裁判資料を自己に不利に援用される可能性のある第三者の利益を損なわないよう、裁判所は弁論の併合に慎重でなければならない。
イ 固有必要的共同訴訟の訴え漏らしの治癒
ただし、固有必要的共同訴訟の場合には、訴えの適法性を維持することについての原告の利益が第三者の利益に優越すると考えられるから、裁判所は弁論の併合を認めるべきである。
※伊藤眞著『民事訴訟法 第7版』有斐閣2020年p683
う 勅使川原和彦氏論文
・・・こうした裁判所の権能を手続裁量として、その著しい逸脱は違法となるとする見解がある(注釈(3)202頁、204頁[加藤)。特に、固有必要的共同訴訟における当事者適格の欠缺の補正のために別訴を提起した上で弁論併合申請をした場合は、併合をしないことが著しい手続裁量の逸脱になるとする。支持すべき”である)。
※勅使川原和彦稿/加藤新太郎ほか編『新基本法コンメンタール 民事訴訟法1』日本評論社2018年p452
6 別訴(新訴)提起における管轄→併合請求扱い
被告として訴え漏らした者に対する訴訟を追加で(別訴として)申し立てる際には、管轄が問題となります。これについては、併合請求(最初の提訴から被告に含めていた場合の扱い)の規定を類推適用する、つまり、先行する訴訟が係属している裁判所に提訴できる、という見解もあります。この規定を使わず、別の裁判所に別訴の申立をした場合には、その後、別訴を、先行訴訟が係属している裁判所に移送した上で併合する、ということが必要になります。
別訴(新訴)提起における管轄→併合請求扱い
あ 併合請求の規定の類推
弁論が併合されるためには、係属中の訴訟と新訴とが同一の裁判所に係属することが必要であるが、その前提として、併合請求の裁判籍の規定(7)を類推適用して、新訴の土地管轄を拡張することが許される。
い 別裁判所への提訴+移送
・・・7条の類推適用が否定されても、別の裁判所に提起された新訴を17条にもとづいて移送し、弁論併合の前提要件を整える可能性もある。
※伊藤眞著『民事訴訟法 第7版』有斐閣2020年p682
7 別訴(新訴)提起における印紙→重複(追加)方向
訴え漏らした者に対する別訴の提起の際に、訴状に貼付する印紙(提訴手数料)の問題もあります。仮に最初から被告に入れておけば、提訴手数料は増えずに済んだはずなので、後から被告を追加する時にも同じように、(追加)の手数料(印紙)は不要、という発想もあります。この点、昭和62年判例は、手数料のことを直接判断していませんが、別の訴訟の提起であるという判断をしているので、(追加の)手数料が必要になる、と読めます。
別訴(新訴)提起における印紙→重複(追加)方向
あ 伊藤眞氏見解→印紙不要
なお、新訴の提起にあたっては、訴額に応じた提訴手数料を納付しなければならないが、訴えをもって主張する利益が共通であるとみなされるときには、手数料の納付がなされない場合でも、裁判長が補正命令の発令や訴えの却下(137III)を行わないことが考えられる。
※伊藤眞著『民事訴訟法 第7版』有斐閣2020年p682
い 昭和62年最判→印紙必要方向
昭和62年最判(後記※2)は別訴(新訴)提起における印紙(手数料)の要否について直接判断していないが、当事者による印紙は不要という主張を否定しているようにも読める
8 訴えの主観的追加的併合
訴えの主観的追加的併合は、別訴提起と弁論の併合に代わる方法で、これにより手続を簡略化できます。この方法を認めると、弁論の併合を認めるかどうかという裁判所の裁量が否定されることになります。学説としてはこのような方法が提唱されていますが、実務・判例は否定しています(後述)。
訴えの主観的追加的併合(※1)
あ 主観的追加的併合の意味
原告X、被告Yの訴訟の係属中において
XのZに対する請求を併合することを申し立てること
これ(主観的追加的併合)を認める明文規定はない
い メリット
(原則的な手法である別訴提起と比較して)Xにとって手続が煩雑にならない
(別訴の訴状と違って)印紙の貼用が不要である
従来の訴訟資料をXZ間の訴訟で用いることができる
審理の重複の防止や裁判の矛盾を避けることができる→紛争の統一的かつ一回的解決を実現できる
(訴訟遅延のおそれがある場合には)弁論の分離で対応すれば足りる
う デメリット
主観的追加的併合を認めると濫訴や訴訟遅延の危険がある
係属中の訴訟手続の結果が当事者の援用・同意なくして新当事者との間の審判に当然に利用できるとは限らない
え 判例
ア 昭和62年最判→否定説
判例は主観的追加的併合を一般的に否定する
当事者としては別訴を提起して裁判所の弁論の併合によるべきである
※最判昭和62年7月17日(後記※2)
イ 過去の裁判例
主観的追加的併合を認めた(肯定説)
※札幌高裁昭和53年11月15日
主観的追加的併合を否定した(否定説)
※大阪地裁昭和46年3月24日
9 主観的追加的併合を否定した昭和62年最判
訴えの主観的追加的併合は、昭和62年最判が否定しました。もともと民事訴訟法上、この方法を認める規定はなく、実質的にも、弁論の併合について裁判所の裁量を否定するのは妥当ではない、ということなどが理由となっています。
なお、別訴提起をした上で弁論を併合する、という手続のことを訴えの主観的追加的併合と呼ぶこともあります(前述のようにこの方法は可能です)。
主観的追加的併合を否定した昭和62年最判(※2)
あ 当事者の主張→追加印紙不要
所論は、要するに、上告人がTを被告として提起している東京地方裁判所昭和五五年(ワ)第八八一号事件の請求(以下「旧請求」という。)と上告人が被上告人を被告として提起している本件訴えにかかる請求とは民訴法(以下「法」という。)五九条所定の共同訴訟の要件を具備しているから、本件訴えを旧請求の訴訟に追加的に併合提起することが許されるべきであるところ、右の両請求の経済的利益が共通しているから、上告人は本件訴えにつき手数料を納付する必要はない、というのである。
い 裁判所の判断(メイン)
しかし、甲が、乙を被告として提起した訴訟(以下「旧訴訟」という。)の係属後に丙を被告とする請求を旧訴訟に追加して一個の判決を得ようとする場合は、甲は、丙に対する別訴(以下「新訴」という。)を提起したうえで、法一三二条の規定による口頭弁論の併合を裁判所に促し、併合につき裁判所の判断を受けるべきであり、仮に新旧両訴訟の目的たる権利又は義務につき法五九条所定の共同訴訟の要件が具備する場合であつても、新訴が法一三二条の適用をまたずに当然に旧訴訟に併合されるとの効果を認めることはできないというべきである。
う 裁判所の判断(理由)
けだし、かかる併合を認める明文の規定がないのみでなく、これを認めた場合でも、新訴につき旧訴訟の訴訟状態を当然に利用することができるかどうかについては問題があり、必ずしも訴訟経済に適うものでもなく、かえつて訴訟を複雑化させるという弊害も予想され、また、軽率な提訴ないし濫訴が増えるおそれもあり、新訴の提起の時期いかんによつては訴訟の遅延を招きやすいことなどを勘案すれば、所論のいう追加的併合を認めるのは相当ではないからである。
※最判昭和62年7月17日
え 補足説明
旧訴と新訴は固有必要的共同訴訟の関係にある事案ではない
10 訴訟告知による当事者欠落の瑕疵の治癒→否定
以上の当事者欠落の治癒の方法とは別に、訴訟告知によって治癒するという発想もあります。しかし、訴訟告知は訴訟提起ではないので、判例は訴訟告知により当事者欠落は治癒されないと判断しています。
訴訟告知による当事者欠落の瑕疵の治癒→否定
あ 事案
原告側について固有必要的共同訴訟を構成するケースについて
原告が所在不明の者に公示送達により訴訟告知をした
い 裁判所の判断
訴訟告知を受けた者は、告知によって当然に当事者または補助参加人となるものではない
※民事訴訟法53条、46条参照
→直ちに瑕疵が治癒されることにはならない
※最判昭和46年12月9日
う 批判
事案の落しどころとしては疑問が残る
※新堂幸司著『新民事訴訟法 第6版』弘文堂2019年p788
11 訴訟係属中の当事者の変更(参考)
以上の説明は、訴訟提起の時点から本来当事者となるべき者が欠落していたという場合の治癒の方法です。この点、訴訟提起の後(係属中)に当事者が変わったという場合には、その治癒(対応)の方法は少し違います。具体的には訴訟継承の手続で済みます。なお、民事訴訟法に訴訟継承の規定がない時代には別訴提起をした上で弁論の併合をする、ということをしていました。
これについては別の記事(共有物分割訴訟に関する記事)で説明しています。
詳しくはこちら|共有物分割訴訟の当事者(共同訴訟形態・持分移転の際の手続)
本記事では、固有必要的共同訴訟における当事者の欠落を治癒する方法について説明しました。
実際には個別的な事情によって法的扱いや最適な対応は違ってきます。
実際に、原告または被告が複数となる訴訟に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。