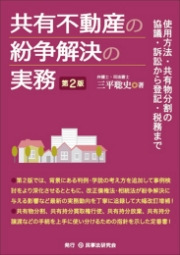【区分所有法22条(分離処分禁止)の敷地利用権の「共有」の要件(分有など)】
1 区分所有法22条(分離処分禁止)の敷地利用権の「共有」の要件(分有など)
区分所有建物は専有部分と敷地利用権の分離処分が禁止されます。
詳しくはこちら|区分所有建物の専有部分と敷地利用権の分離処分禁止
分離処分が禁止されるのは、敷地利用権が共有となっている場合です。通常はこれに該当しますが、特殊な状況では、「共有」ではないため分離処分は禁止されないこと、あるいは、「共有」ではあるけれど例外的に分離処分は禁止されない、ということがあります。本記事では、この問題について説明します。
2 分離処分禁止の条文規定
最初に、条文を確認しておきます。
基本ルールは1条です。条文はシンプルで、敷地利用権を「数人で有する」つまり「区分所有者で(準)共有する」場合に、専有部分と敷地利用権の分離処分が禁止されます。これは、分離処分禁止の基本ルールといえます。
基本ルールだと、敷地利用権を「単独で有する」場合には分離処分禁止は発動しないはずです。その場合でも、全部の専有部分を1人が所有している場合には、例外的に分離処分禁止は発動する、というサブルール(3項)があります。
分離処分禁止の条文規定
第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
3 前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。
※区分所有法22条
3 分有方式の共有要件充足性→否定
区分所有建物だけど敷地が共有ではないという特殊なケースがあります。それは、タウンハウスで利用される分有方式の場合です。
タウンハウスとは、専有部分が壁を隔てて横に繋がり1棟の建物となっている建物です。
その1棟の建物の敷地は、専有部分ごとに分割(分筆)されていることが多く、その場合、区分所有者は専有部分直下の分割された1筆の土地を単独で所有します。このような敷地の所有形態を分有と呼びます。
分有方式の場合、敷地利用権は共有されていないので、前述の基本ルール(1項)が適用されません。つまり、専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができます。
敷地利用権が共有になっていないので、分離した処分をしても権利が複雑化しない(通常の戸建と同様である)と考えられているのです。
分有方式の共有要件充足性→否定
あ 敷地利用権の形態の種類(前提)
・・・
②一部のタウンハウスにおいて見られるように、区分所有建物の敷地が各専有部分ごとに区画されて一筆とされ、各区分所有者がその区画について単独で所有権、地上権、賃借権などを敷地利用権(分有形式の敷地利用権)として有している場合(2条の注釈〔7〕(2)参照)、
または、
区分所有者が敷地を分有しながら、分有敷地の垂直上下空間外に専有部分を有する場合である(10条の注釈[2]参照)。
い 分有方式の共有要件充足性(まとめ)
本条1項でいう、「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合」とは、①の場合をいう。
土地が分有に属する②の場合はいずれも、本条の一体性(分離処分の禁止)の制度が適用されない。
う 分有方式の共有要件充足性(所有権)
敷地利用権を数人で有するという場合に、(2)で述べたように、その態様としては、区分所有者が、敷地利用権を共有持分の形で有する場合と分有の形で有する場合とがある
(たとえば、ABが区分所有する建物の敷地がABの共有である場合にはABは敷地利用権を共有持分として有し、ABが区分所有する建物の敷地がABの分有である場合にはABは敷地利用権をそれぞれ単独所有権として有する)。
本条の適用があるのは、共有持分の形で有する場合に限られる。
え 分有方式の共有要件充足性(所有権以外の権利)
敷地利用権が数人で有する地上権、賃借権等である場合には、区分所有者は、敷地利用権を地上権、賃借権等の準共有持分の形で有するか、準分有の形で有するかである
(たとえば、ABが区分所有する建物の敷地が第三者の所有である場合に、ABは、敷地利用権を地上権、賃借権等の準共有持分として有するか、ABそれぞれの地上権、賃借権等として有する)。
準共有持分の形で有する場合のみ本条の適用がある。
※稲本洋一郎ほか著『コンメンタール区分所有法 第3版』日本評論社2015年p130、131
4 専有部分A所有・B所有・敷地利用権AC共有→適用あり
分離処分禁止の要件である「共有する」にあてはまるかるかどうか、はっきりしないことがあります。以下、これが問題となるケースを説明します。
ところで、区分所有者と敷地の共有者が全部一致しているケースであれば所有権を、全部一致していないケースであれば何らかの利用権を「共有する」ことになり、単純です。
しかし、区分所有者と敷地共有者の一部「だけ」が一致しているケースではどうでしょう。
まず、区分所有者の一部の者だけが敷地を共有(所有)するケースを考えます。たとえば、専有部分がA所有、B所有で、敷地はACの共有となっているケースです。
仮に、土地について、ACを賃貸人、ABを賃借人とする賃借権が設定(Aについては自己借地権)されていれば、敷地利用権(賃借権)をABで共有することになるので、分離処分禁止が適用されます。
専有部分A所有・B所有・敷地利用権AC共有→適用あり
(たとえば、ACを賃貸人、ABを賃借人とする賃貸借関係がある場合には、Aの敷地利用権は所有権ではなく賃借権となる。
なお、借地借家法15条1項参照)。
この場合には、敷地利用権をABで有する関係にあり、本条の適用がある。
※稲本洋一郎ほか著『コンメンタール区分所有法 第3版』日本評論社2015年p131
5 専有部分A所有・B所有、敷地利用権ABC共有→適用なし
前述の一部一致のケースのうち、敷地共有者が区分所有者を包含するパターンについて説明します。たとえば、専有部分がA所有、B所有で、敷地がABC共有というケースです。
この場合には、結論として、Cの共有持分は自由に処分することができる、という扱いになります。
敷地利用権とは「専有部分を所有するための権利」のことであり、専有部分を所有しないCの共有持分は、敷地利用権ではないからです。そもそも、専有部分を所有していないCの立場では、専有部分と敷地利用権を分離する(あるいはしない)、ということができません。
なお、この場合のA、Bは専有部分と敷地利用権との分離処分が禁止されるので、例えばBがCに専有部分を売却するときでも、敷地利用権と一緒に売却することになります。
その結果、Cは専有部分との分離処分が禁止される敷地利用権(に該当する共有持分=Bから譲り受けた共有持分)と、禁止されない(従前から持っていて、敷地利用権に該当しない)共有持分とを持つことになります。
専有部分A所有・B所有、敷地利用権ABC共有→適用なし
したがって、Cが従前から有する敷地の共有持分は、Cの取得した専有部分と分離して処分することができる。
※稲本洋一郎ほか著『コンメンタール区分所有法 第3版』日本評論社2015年p132
6 全部の専有部分を単独所有しているケース
前述の基本ルール(共有要件)では、専有部分が複数あっても、その所有者が1人である場合には、敷地利用権が共有になっていないため、分離処分禁止のルールは適用されないことになります。
しかし、それだと困ることがあるので、もう1つのサブルール(3項)があります。それは、1人が全部の専有部分を所有していて、かつ、敷地利用権を単独で所有するときは、分離処分が禁止される、というものです。
この規定が意味を持つ典型は、新築のマンションを分譲するときです。事業者が敷地を取得し、その上に分譲マンションを建設すると、その事業者がすべての専有部分の所有者となり、かつ、敷地利用権はその事業者の単独所有となります。この場合、基本ルールだけでは分離処分を禁止することができません。そのため、サブル-ルが定められているのです。
さらに、AとBが全部の専有部分を共有している(敷地利用権もAとBが共有する)場合にも、同じような状況といえるので、分離処分禁止のルールが適用されるという見解が一般的です。具体例は、2つの事業者が共同して新築マンションを分譲するような場合です。
これらのことから、基本ルールの「敷地利用権を数人で有する」とは、複数の専有部分の所有者によって敷地利用権が共有されることを想定した規定だといえます。
全部の専有部分を単独所有しているケース
あ 分譲業者
〔9〕本条1項および2項の準用
本条1項および2項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用される(本条3項)。
(1)準用の趣旨
本条1項の適用に当たっては、「敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合」に限定されるので、敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合においては、その適用要件を欠くことになる。
そうすると、土地について単独で所有権等の権利を有する者が、地上に区分所有建物を建築してその専有部分の全部を原始的に所有しているような場合においては、その各専有部分と敷地利用権とが分離して処分されることが許されることになってしまう。
このような場合においても、各専有部分とその敷地利用権が一体的に譲渡されることが望ましく、本条1項の適用を排除する合理的理由は何もない。
そこで、本条3項では、本条1項および2項の規定は建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用される、と規定した。
※稲本洋一郎ほか著『コンメンタール区分所有法 第3版』日本評論社2015年p138
い 専有部分も共有
(3)敷地利用権共有者による専有部分全部の共有
土地を共有し、または地上権、賃借権を準共有する者が、その地上に区分所有建物を新築して、その専有部分全部を共有する場合に、本条3項の適用があるか
法務省立法担当者は、本条1項および2項の規定が直接に適用されるのではなく、本項で規定する場合と実質上事態が異ならないから、本項の規定が(類推)適用され、このことによって本条1項および2項の規定が準用されるべきであると解している(濱崎・解説182)。
妥当であろう(なお、東京地判平4・5・6判時1453-137判夕801-175参照)。
※稲本洋一郎ほか著『コンメンタール区分所有法 第3版』日本評論社2015年p139
7 分有方式の3項該当性→両説あり
ところで、前述のサブルールが適用されることによって、禁止しなくてもよい分離処分まで、禁止されてしまうことがあります。
それは、新築された分譲建物がタウンハウスで、敷地利用権が分有形式であった、というケースです。本来、このケースでは敷地利用権が共有されないことから、基本ルールの要件にあてはまらず、専有部分と敷地利用権の分離処分は禁止されません(前述)。しかし、「専有部分の全部を単独で所有し、かつ、敷地利用権を単独で所有する」、というサブル-ルの要件にあてはまります。そのため、分譲の際には分離処分の禁止が適用されます。
問題なのは、専有部分とその直下の分有された敷地利用権を一体として売却する場合でも、それが分離処分に該当すると解する余地があることです。たとえば、1号室と2号室の2つの専有部分からなるタウンハウスがあり、1号室とその直下の敷地を一体として売却する状況です。
この点については、分離処分に該当する(サブル-ルが適用される)ことを前提に、分譲の際には分離処分を可能とする規約を設定しなければならない、とする見解と、敷地が分有形式なのだから分離処分にはあたらない、とする見解があります。
分有方式の3項該当性→両説あり
一部のタウンハウスにおいて見られるように、区分所有建物の敷地が各専有部分ごとに区画されて一筆とされ、各区分所有者がその区画について、単独で、所有権、地上権、賃借権などを敷地利用権(分有形式の敷地利用権)として有している場合には、本条3項の適用がなく、したがって、本条1項の規定が準用されることはない(前記〔2〕(2)参照)。
しかし、このようなタウンハウス形式の建物を新築して、その専有部分全部を単独で所有し、かつ、単独で所有する土地を各専有部分ごとに分筆して譲渡することを予定する場合には、本条3項の適用があり、したがって、本条1項および2項の規定が準用される。
この場合には、「専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合」に該当するからである。
その結果、各専有部分を分譲する場合に、それに対応する敷地利用権を分離して処分することができない。
ただし、この場合に、分有形式の敷地利用権の譲渡は、当該譲受人以外の譲受人との関係では、分離処分となると解して本条1項ただし書の規約の設定を必要とするか、または分離処分に当たらないとして規約を設定することを要しないとするかは議論の余地があろう。
法務省立法担当者は、本条1項ただし書の規約を定めることが必要である(濱崎・解説182)と解しているが、分有形式をもって分離処分と見る必要はなく、規約による定めを要しないと解すべきである。
※稲本洋一郎ほか著『コンメンタール区分所有法 第3版』日本評論社2015年p139
本記事では、区分所有建物の専有部分と敷地の分離処分禁止における「共有」の要件について説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に区分所有建物の分離処分に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。