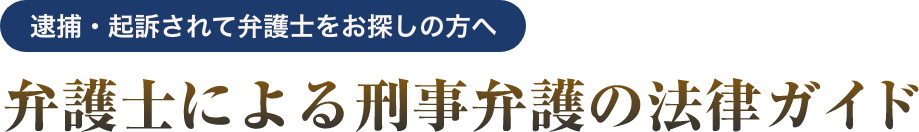【代理・代表名義の冒用による私文書偽造罪(刑法159条)(解釈整理ノート)】
1 代理・代表名義の冒用による私文書偽造罪(刑法159条)(解釈整理ノート)
AがBに無断で「B代理人A」という名義の署名や押印をした場合はどうでしょうか。民事上は代理権がないため、原則としてAに効果が帰属しないなど、細かいルールが形成されています。一方、刑法上は私文書偽造罪が成立するかどうか、という問題があります。本記事では、代表・代理名義の冒用(無断使用)ケースにおける私文書偽造罪の成否に関する解釈を整理しました。
2 刑法159条の条文
刑法159条の条文
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
※刑法159条
3 問題の所在→「名義人が誰か」によって偽造の成否が決まる
問題の所在→「名義人が誰か」によって偽造の成否が決まる
4 名義人の解釈→判例通説は有形偽造説
(1)判例→名義人は本人(有形偽造説)
判例→名義人は本人(有形偽造説)
あ 結論→名義人は本人
判例は名義人を本人(冒用された者)とみるため、有形偽造になると解している
い 判例
ア 明治42年大判
代理者資格を詐称して文書を作成する行為は、直接に他人の署名を冒用する場合と同様に刑法159条1項の犯罪に当たるとした
※大判明治42年6月10日
イ 昭和45年最決
他人の代理人又は代表者として文書を作成する権限のない者が、他人を代理・代表すべき資格を表示して作成した文書の名義人は、代理・代表された本人と解すべきであるとしている
※最決昭和45年9月4日
(2)学説→見解が分かれる
学説→見解が分かれる
あ 有形偽造説(通説)
代理・代表形式の文書は本人のために作成され、その法的効果が本人に帰属するから、名義人は本人であり、代理資格・代表資格を持たない者がその資格を冒用してこれらの文書を作成する行為は、有形偽造に当たるとする
い 無形偽造説
無権代理・無権代表の部分は単なる肩書きにすぎず、名義人は作成者自身であるから、文書は真正文書であり、虚偽記載であるため無形偽造であるとする
う その他の学説
(ア)有形偽造拡張説(イ)無権偽造説(ウ)裁可名義説・帰責名義説
(3)有形偽造説(判例・通説)への批判
有形偽造説(判例・通説)への批判
民法99条1項は意思表示の主体(代理・代表形式の文書の名義人)は代理人又は代表者であるという理解が前提となっている
法的効果の帰属を理由に名義人を本人とするのは整合性を欠くという批判がある
(4)実務における判断の要点
実務における判断の要点
判例・通説は「文書に記載された法的効果の帰属先」を名義人と考える
代理・代表形式で作成された文書の名義人は本人(被代理者・被代表者)である
代理・代表資格のない者がその資格を冒用して文書を作成した場合、名義人である本人の名を偽ったことになり、有形偽造となる
5 関連テーマ
(1)代理人の顕名の認定(肩書だけ・署名代理など)
詳しくはこちら|代理人の顕名の認定(肩書だけ・署名代理など)(解釈整理ノート)
6 参考情報
参考情報
本記事では、代理・代表名義の冒用による私文書偽造罪について説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に代理・代表名義の冒用による私文書偽造罪に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。