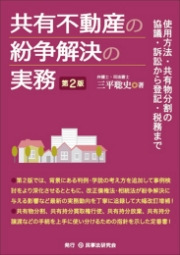【離婚後の元夫婦間の共有物分割(経緯・実例)】
1 離婚後の元夫婦間の共有物分割(経緯・実例)
夫婦間で共有物分割をすることは、そもそも認められるかどうか、ということも含めていろいろな法的な問題があります。
詳しくはこちら|夫婦間の共有物分割請求の可否の全体像(財産分与との関係・権利濫用)
この点、離婚によって夫婦関係を解消した後に、つまり元夫婦の間で共有物分割をするケースもあります。この場合にも、共有物分割が認められるかどうか、という問題が出てくることがあります。
本記事では、元夫婦間の共有物分割について、どうして離婚後に財産の清算をすることになるのか(経緯)や、権利の濫用にならないかということ、そして特有の検討事項(特徴)を、実例を紹介しつつ説明します。
2 離婚後に共有物分割をすることになる経緯
普通であれば、離婚の際に夫婦の財産関係も財産分与として清算(解決)することになります。しかし、住宅ローンが残っているため、第三者に売却できず、そのまま(夫婦の共有のまま)にしておくことがあります。
協議離婚で夫・妻とも不動産については何もしようと思わなかったケースもあれば、財産分与の審判や離婚訴訟を行ったのに、裁判所が意図的に清算しなかった、というケースもあります。
離婚後に共有物分割をすることになる経緯
あ 財産分与自体未了
離婚の時に夫婦のいずれも財産分与の請求自体をしなかった
い オーバーローンによる財産分与否定
共有不動産がオーバーローンであったため、裁判所が財産分与の対象から除外する方法を採用した
詳しくはこちら|財産分与におけるオーバーローン不動産の扱い(全体で通算か清算対象からの除外)
う 特殊事情による財産分与否定
担保の状況などが複雑であることを理由に、裁判所が財産分与をしないという判断をすることがある
詳しくはこちら|財産が複雑であるため財産分与請求を棄却した裁判例(消長見判決)
3 元妻+子居住→妻が取得(全面的価格賠償・平成26年東京地判)
離婚の時の夫婦間の合意によって、離婚後も、元夫婦の共有となっていた不動産に元妻と子が居住していたケースです。元夫が共有物分割訴訟を申し立てました。元妻は、権利の濫用である、と主張しましたが裁判所は採用しませんでした。
ポイントは、離婚時の合意で、居住させる義務を決めたがこれが無期限ではないということと、夫は離婚後にも住宅ローンの返済を続けていたけれど、経済的に返済の継続が困難となっていた、という事情でした。
一方、元妻は(親族からの援助により)夫の共有持分の価値程度の金銭を支払うことができる状況にありました。そこで結論として裁判所は妻が取得する全面的価格賠償を採用しました。結果的に元妻子の居住は確保された、ということになります。
また、裁判所は、登記された共有持分割合とは違う共有持分割合を認定しました。この点、共有物分割訴訟では登記で権利の判定をすることがありますが、このケースではその判定方法を使わない状況だったのです。なお、持分割合の判断に既判力は生じないので、理論的には別の訴訟でくつがえされるリスクがあります。被告としては反訴として持分確認請求(訴訟)の申立をするとベストでしたが、この事案の被告は反訴をしていません。
詳しくはこちら|共有物分割(訴訟)の当事者(共同訴訟形態)と持分割合の特定
次に、賠償金の金額算定では、一般論としては、住宅ローンの残額の控除をすることもあります。
詳しくはこちら|全面的価格賠償の賠償金算定における担保負担額の控除
この裁判例では、住宅ローン残額の控除はしませんでした。というのは、元妻が元夫に支払う賠償金は約2300万円であり、元夫はこれにより、ローン残額約1300万円を完済できることになります。そこで、元妻は抵当権実行により当該不動産を失うリスクはほぼないといえる状態だったのです。
一方、賠償金の算定で、過去の住宅ローンの返済のうち、妻の特有財産から支払った部分を控除しました。
この手法は、夫婦間の清算として離婚に伴う財産分与で用いる手法ですが、一般的な共有物分割では通常用いない手法です。なお、この事案では、離婚から2年が経過していたため、財産分与は請求できないという状況にありました。ある意味、共有物分割訴訟の中で実質的な財産分与(夫婦間の清算)を行ったともいえるでしょう。
元妻+子居住→妻が取得(全面的価格賠償・平成26年東京地判)
あ 登記とは異なる持分割合の認定
本件不動産については、原告の持分を100分の87、被告の持分を100分の13とする本件共有登記がされており、原告は本件不動産が被告との共有であることを前提に共有物分割を求めているところ・・・
・・・被告が本件不動産の頭金として負担した額は合計961万5000円となる。ところで、本件不動産の売買代金額が4230万円であることは当事者間に争いがないものの、原告と被告は、頭金1773万円と本件住宅ローン2770万円の合計4543万円を本件不動産の取得に費やしているから、原告と被告の実質的な負担割合からその持分割合を検討するには、4543万円を100として負担割合を検討するべきである。そうすると、被告の負担額の割合は21.2%となる。そして、上記で認定した事実によれば、原告と被告との間では、婚姻期間中に返済が予定されていた原告名義の本件住宅ローンに係る部分は別として、負担額に応じて本件不動産の持分を取得する意思であったと推認されることからすれば、被告は上記負担により本件不動産の持分100分の21を取得したと認めるのが相当である。
い 権利濫用→否定
・・・被告は、本件合意書に基づき、長男らとともに住居費の負担をせずに本件不動産に居住し、原告から長男らの養育費及び生活費として月額25万円を受領していたが、・・・
そして、本件不動産が共有物分割されることになれば、被告が住居費の支出を要するに至る可能性が高いと認められる。
しかしながら、上述したように、本件合意書は合意の内容を定期的に見直すとしている上、原告が本件合意書により、被告に対し、本件不動産の分割請求をしないとまでの約束をしたとは認められないし、期限なく被告が住居費を支出する必要がない状態を継続させる義務を負ったとまでは認められない。
また、・・・原告は、平成21年1月1日に再婚し、長男らの他にも扶養家族を有するに至っていること、原告は、平成23年2月1日には本件住宅ローンの債権者に対し、同年3月から平成26年2月までの3年間の返済月額を減額する償還条件の変更を申し入れたこと、同条件変更により平成26年2月以降の返済額が月額16万円以上となることが予定されていたこと・・・、原告が本件合意書で合意していた長男らの養育費等は、被告の申し立てた養育費に関する審判において月額で10万円の減額がされていることが認められる。
これらに照らせば、被告の収入が年200万円に満たないことを考慮したとしても、本件不動産の共有物分割が原告の権利濫用であるとまでは認められないというべきである。
う 全面的価格賠償の相当性→居住により肯定
本件不動産は、原告と被告がその婚姻中に、原告、被告及び長男ら家族の住居として取得されたものであり、上述したように、原告と被告がそれぞれ頭金を負担したことから、その負担割合に応じた共有持分を有することになったものである。
・・・
そして、被告は、本件合意書に基づき、本件離婚後も長男らと本件不動産における居住を継続しており、長男らが未成年であり、学業に従事している年齢にあることからすると、被告が本件不動産の取得を希望することには合理性がある。
これに対し、原告は、他に居住しており、本件不動産の取得を希望していないことからすれば、被告に本件不動産を取得させることには相当性があると認められる。
え 抵当権負担による相当性阻却→否定
もっとも、本件不動産には、本件住宅ローン債務を被担保債権として、原告を債務者とする抵当権が設定されており、本件口頭弁論終結時における債務残高は1289万2956円であるところ、被告が本件不動産を取得するとしても、同抵当権が設定されたままの状態となるから、このような状態で本件不動産を被告に取得させることは相当ではないとも思われる。
しかしながら、被告がこの状態を認識しながら全面的価格賠償による分割を希望していること、被告が本件不動産の所有者となれば原告の債務である上記被担保債権の弁済や求償等、法的な対処が可能となると解されることからすれば、上記抵当権の存在を考慮しても、被告に本件不動産を取得させることが相当であるというべきである。
お 適正評価
ア 客観的評価
次に、本件不動産の適正な評価額が問題となるところ、・・・本件不動産の価格は3800万円と認めるのが相当であり、この認定を覆すに足りる証拠はない。
そうすると、上記1(2)で認定説示したように、原告と被告の本件不動産の持分割合はそれぞれ100分の79と100分の21であるから、原告の持分に相当する価格は3002万円となることになる。
イ 住宅ローン返済原資(寄与の程度)
ところで、本件住宅ローンの返済のうち平成15年11月から平成16年2月まで及び同年11月から平成20年6月までの合計48か月分合計563万5536円は、原告と被告との婚姻中に原告の得た収入から支払われたものであること、及びその支払額の2分の1である281万7768円について被告の寄与が存在することは当事者間に争いがない。
・・・
平成18年1月19日に行われた499万5132円の繰上返済は、被告の固有財産によりなされたものと認めるのが相当である。
・・・
以上によれば、平成15年11月から平成16年2月まで及び同年11月から平成20年6月までの合計48か月分の本件住宅ローンの合計563万5536円の2分の1である281万7768円、及び499万5132円の繰上返済の合計781万2900円については、原告と被告との共有関係の解消にあたり、被告が支払うべき代償金の算定において、被告が本件不動産の取得等に関し行った寄与として考慮するべきである。
この場合、本件不動産の価格が調達資金額合計4543万円から3800万円に下落していることからすると、この下落率と同様の比率により上記金額を減縮して評価するべきであり、その額は653万5100円となる。
ウ 賠償金(代償金)の金額
以上によれば、本件不動産について全面的価格賠償による分割を行う際に被告が原告に支払うべき代償金の額は、3002万円から653万5100円を控除した額に相当する2348万5000円と定めるのが相当である。
か 結論→全面的価格賠償
本件不動産を被告の所有とし、被告には原告に対し2348万5000円の代償金の支払を命じる方法の分割を行うことは、原告と被告との実質的公平を害しないと認められる。
※東京地判平成26年10月6日
4 元妻居住+第三者への賃貸→換価分割(平成17年東京地判)
離婚後に、元夫婦の共有の建物に、元妻が居住していたケースです。夫が共有物分割訴訟を申し立てました。裁判所は、消去法的に換価分割を選択しました。
結局、元妻は退去することになる、という結論となりました。
元妻居住+第三者への賃貸→換価分割(平成17年東京地判)
あ 事案
土地・建物が、元夫と元妻それぞれ2分の1の共有となっていた
建物の一部に妻が居住し、他(残部)は第三者に賃貸されていた
元夫が共有物分割を請求した
い 裁判所の判断
現物分割は困難であった
両者ともに相手方の持分相当額を支払う資力がなかった
裁判所は、換価分割を選択した(共有物分割請求自体は否定しなかった)
※東京地判平成17年2月18日
本記事では、離婚後の元夫婦間の共有物分割について説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的扱いや最適な対応方法は違ってきます。
離婚後の共有物分割などの共有不動産に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。