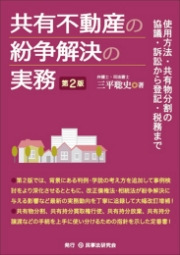【共有不動産への賃借権設定登記申請の当事者(令和5年通達)】
1 共有不動産への賃借権設定登記申請の当事者(令和5年通達)
令和3年の民法改正で、賃貸借のうち、一定の期間に満たないケースは管理分類(過半数持分で決することができる)ことが明文化しました(民法252条4項)。
詳しくはこちら|共有物の賃貸借契約の締結の管理行為・変更行為の分類
これに伴い、賃借権設定登記の申請で、共有者のうち過半数持分を有するものだけが申請人となれば足りる、という運用が始まっています。本記事ではこのことを説明します。
2 令和5年法務省通達(登記義務者・申請人は誰か)
令和3年改正を受けて、令和5年に示された登記に関する通達があります。
この通達ではまず、登記申請の説明の前提として、短期賃貸借の契約の賃貸人(当事者)は、賛成した共有者(持分過半数)の全員またはその一部である、という説明がなされています。反対共有者も含めた共有者全員ということを否定している、つまり授権を否定しているようにも読めます。
詳しくはこちら|共有不動産の賃貸借契約における賃貸人の名義(反対共有者の扱い)
その上で、登記申請については、反対共有者も登記義務者に含むが、申請人には含まないという説明になっています。これは、申請意思がない以上、申請人になれないが、賃借権設定は、所有権(共有持分権)の制限になるので、共有者全員が「登記上、直接に不利益を受ける」(不動産登記法2条13号)に該当するということが理由です。反対共有者にも賃貸借契約の効果が及ぶという意味ではありません。
次に、長期賃貸借については、共有者全員の同意が必要であるところ、賃貸人となるのは共有者全員でもよいが、共有者の一部でもよいという説明がなされています。登記申請については通達では説明がないですが、共有者全員が登記義務者となり、かつ申請人となる、ということは当然です。
令和5年法務省通達(登記義務者・申請人は誰か)
あ 短期賃貸借
ア 賃貸人→賛成共有者全員またはその一部(前提)
(2)前記(1)の過半数で決するところにより短期の賃借権等が設定され(当該過半数による決定を行った共有者全員が契約当事者になる場合と、その一部が契約当事者になる場合がある。)、
イ 登記申請人→過半数持分権者・登記義務者→共有者全員
これに基づいて当該短期の賃借権等の設定の登記を申請する場合には、改正民法第252条第4項の趣旨から、各共有者の持分の価格に従い、その過半数を有する共有者らが登記申請人となれば足りる(当該共有者ら以外の共有者らは、登記申請人とはならないが、登記義務者としてその氏名又は名称及び住所を申請情報の内容とする必要がある。)。
※法務省民事局長令和5年3月28日『法務省民二第533号』通達p3、4
い 長期賃貸借
ア 賃貸人→共有者全員または一部(前提)
(注・共有物の管理者による長期賃貸借の説明の箇所)
共有物の管理者が共有物について長期の賃借権等を設定し(管理者自らが契約当事者になる場合と、共有者の全部又はその一部が契約当事者になり、管理者がこれらの者から委任を受けて契約を締結する場合がある。)、・・・
※法務省民事局長令和5年3月28日『法務省民二第533号』通達p7、8
イ 登記申請人・登記義務者→共有者全員
(当然、従前と変わりはない)
3 登記申請における登記所の変更・管理分類の判定の問題
(1)登記所(登記官)による判定の問題
令和5年通達の内容は単純ですが、実際には、共有不動産を対象とする賃貸借は、期間だけで変更、管理のどちらに分類されるかが決まるわけではありません。借地借家法の法定更新の適用の有無、当該不動産が賃貸用に建築されたものかどうか、その他の個別的事情によって判断されることになっています。
たとえば、期間2年の建物賃貸借でも普通借家であれば変更分類、と判断される可能性が高いです。期間1年の建物所有目的の土地賃貸借は法定期間30年が適用される(変更分類)のが原則ですが、一時使用目的であれば約定の1年のまま(管理分類)です。
詳しくはこちら|共有物の賃貸借契約の締結の管理行為・変更行為の分類
実際に賃借権設定登記の申請があった時に、法務局(登記官)がどこまで判断するのか、ということが問題になります。一般論として登記官には形式的審査権限(後述)がないとされていますが、これは実体法の判断に踏み込まない、という意味ではなく、申請内容(書面)だけを判断材料とする、という意味であると考えられます。実務の現場では混乱が想定されます。
(2)登記官の形式的審査権限(登記申請一般論・参考)
前述のように、登記申請における法務局(登記官)の審査は形式的審査権限にとどまりますが、これは判断材料レベルの話しであり、実体法の判断を含まないという意味ではありません。
登記官の形式的審査権限(登記申請一般論・参考)
あ 藤原勇喜氏見解―書面審査―
このように我が国の不動産登記制度は、その登記の真正を保持するため、その申請が適法であり、かつ正確であるかどうかを登記原因証明情報等による書面審査によって、その登記原因等の正確性、有効性、適法性等を審査する。
単に形式的な事項のみを審査すればよいわけではない。
形式審査といわれることもあるが、形式審査というと氏名、住所、不動産の所在、面積等の形式的な事項のみを審査すればよいとの誤解が生ずるおそれがあるので、ここでは書面審査と呼ぶことにする。
書面審査というのは書面による実質審査であり、実体法上の有効・無効を判断する必要があるのである。
ただ、その判断資料は申請書・添付情報に限られるということで、書面審査といっているのである。
登記原因の真偽つまり有効・無効を確認するために当事者の出頭を求め、供述を得るといったことはできないということである。
形式的審査権の概念は、審査の対象が登記手続法上の正確性、適法性等に限られる審査というよりも、審査の資料が登記簿、申請情報及び添付情報に限られる審査という意味で用いるのが適切であると考えられる。
登記の申請がされた場合における登記官の審査の資料が登記簿、申請情報及び添付情報に限られる場合にも、審査の対象は、法定の却下事由の有無であって、却下事由の中には、実体法上の判断を必要とするものも含まれている。
例えば、不登法25条13号は、「前各号に掲げる場合のほか、登記すべきものでないときとして政令で定めるとき。」と規定し、それを受けて登記令20条8号では、「前各号に掲げるもののほか、申請に係る登記が民法その他の法令の規定により無効とされることが申請情報若しくは添付情報又は登記記録から明らかであるとき。」と規定していることからも明らかなように、審査の対象が登記手続上の適法性、正確性等に限られることになるわけではない。
※藤原勇喜著『不動産の共有と更正の登記をめぐる理論と実務』日本加除出版2019年p137
い 昭和39年千葉地判
しかし登記官の審査権限は、その審査の対象たる事項に関する問題としてみれば、単に登記申請が手続法的要件を具備しているかどうかだけでなく、申請にあたつて提出された書面により可能な限度で、実体法上の事項についても審査することができ、しかしてかような意味での実体法的事項の審査には実体法自体の解釈を必要とし、またこれを避けえないものであることは多言を要しない。
※千葉地判昭和39年9月29日
4 過半数持分権者による一時使用目的の借地の登記申請→可能
ところで土地の賃貸借や地上権設定を期間5年以下で行うことは可能ですが、借地、つまり建物所有目的の土地の賃貸借(や地上権設定)は最低の期間(法定存続期間)は30年です。
詳しくはこちら|借地借家法の借地期間の基本(法定期間は30年→20年→10年)
そこでこの場合、民法252条4項の上限である5年を超過するので一律に長期扱い(変更分類)となります。過半数持分権者によるこれらの登記申請はできません。
しかし、借地であっても、一時使用目的であれば法定存続期間の適用はありません。
そこで、期間5年、建物所有目的、一時使用目的(登記申請としては「臨時建物所有」目的)という登記申請であれば、過半数持分権者が行うことができるはずです。さらに期間の定めなしという方法も可能です。
なお、この一時使用目的かどうか、という判断については、法務局では資料による審査はしない扱い、つまり自己申告となっています。
詳しくはこちら|一時使用目的の借地の基本(30年未満可能・法定更新なし)
5 共有者による変更分類の賃借権設定登記→公正証書原本不実記載等罪
前述のように、登記申請の時に登記官が変更、管理の分類を正確に判断できない状況が生じます。
そうすると、「過半数持分権者が賃貸人である賃貸借」を管理分類だと判断して賃借権設定登記申請を受理し実行した後に、訴訟において変更分類であると判断される、というケースが想定できます。
この場合、結果的に不実の(実体を欠く)登記をしてしまったことになります。所有者(共有者)は登記名義人(賃借人)に対して抹消登記手続を請求できることになります。
さらに、形式的には公正証書原本不実記載等罪にあたります。
詳しくはこちら|公正証書原本不実記載等罪の基本(条文と公正証書の意味)
この点、法解釈の誤りについて、民事では救済されることがありますが、刑法上は故意を否定できないことになっています(刑法38条3項)。
詳しくはこちら|民法における法律の錯誤(無効・取消の対象となる)
これはあくまでも理論的な検討です。実際には法務局も受け付けたということもあるので、処罰されるに至るようなことはないと思います。いずれにしても、変更・管理分類の判定の問題はこのように拡がってしまうと思います。
6 共有不動産の賃貸借・地上権などが妨害的に使われる実情
(1)想定される状況
ところで、一般論として、共有不動産を目的とする賃貸借契約は、共有者間の対立の中で、妨害的に行われることもあります。典型例は、共有物分割の協議や訴訟の前後に、共有者の1人が第三者に賃貸する、という手法です。
令和5年通達が出たため、過半数持分を有する共有者であれば、賃借権設定登記まで行うことができるようになりました。妨害目的で賃借権登記が活用されてしまうことも想定できます。
(2)共有不動産の賃貸借契約が妨害的に使われた実例
裁判例の中にも、共有者の1人による賃貸借契約が妨害の手段として使われたものは出てきています。ここで紹介する事案は、共有物分割訴訟の直前に、共有者Tが、Tが実質支配する法人との間で賃貸借契約を締結した、というものです。
この事案では、共有物分割は換価分割判決で終わり、その後の形式的競売で賃借権の扱いが問題となりました。この点、Tの持分割合が過半数に達していなかったので、賃借権としては適法ではないことになり、引渡命令は無事発令されました。逆に、Tの持分割合が過半数であれば、賃借権は適法となり、共有者全員に対しても、買受人に対しても対抗できることになったはずです。
共有不動産の賃貸借契約が妨害的に使われた実例
あ 賃借人と共有者の実質的な同一性
抗告人は、昭和五九年一二月二八日に・・・を営む目的で設立され、資本金は一〇〇〇万円、株式の譲渡につき取締役会の承認を条件として定めるいわゆる小規模閉鎖会社で、宅建主任の資格を有するTが代表取締役を務め、Tの住所地を本店所在地とするなど、実質的には代表者であるTの個人企業ともいえる実体にある。
い 賃貸借契約の締結
Tらと抗告人間には、上記共有物分割請求訴訟の提起される直前の平成七年一月四日付けで、本件建物につき期間三年、賃料月額一万五〇〇〇円、敷金一〇万円、利用目的商品置場との約定の賃貸借契約書が作成され、同年八月三一日には同旨の賃貸借契約公正証書が作成されている。・・・
う 妨害目的の認定
・・・上記認定のとおりの抗告人の実体及び共有物分割請求訴訟の提起される直前に、K(注・他の共有者)の同意・協議もなく締結されたことなどの諸事情を総合考慮すれば、上記賃貸借契約は、適正な共有物物件の競売手続を妨害する目的でなされた”ものというほかはなく、この観点からしても抗告人には引渡命令の発令を妨げるべき正当な理由はないというべきである。
※大阪高決平成10年11月13日
(3)過半数持分権者による地上権・地役権設定登記も可能
なお、令和3年改正の民法252条4項では、地上権、地役権といった用益物権の設定も、所定期間以下のものであれば管理扱いとするルールが創設されました。
詳しくはこちら|共有不動産への用益物権設定の変更・管理分類(賃貸借以外・改正民法252条4項)
過半数持分権者が第三者に対して5年以内の地上権や地役権を設定し、登記する、ということも可能になっています。
(4)短期賃貸借保護制度の悪用の歴史(参考)
短期賃貸借の悪用といえば、平成15年で廃止された短期賃貸借保護制度が思い出されます。この制度の悪用が横行し、それを予防するために、抵当権者による形式的な賃借権設定仮登記の活用が広がった、という皮肉な現象が生じました。
詳しくはこちら|短期賃貸借保護制度の悪用の歴史(=平成15年改正で廃止される経緯)
過半数持分権者による賃借権や地上権などの登記も、有用な活用ももちろんできますが、悪用されるケースも出てきてしまうように思います。
本記事では、共有不動産についての賃借権設定登記の当事者について説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に共有不動産の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。