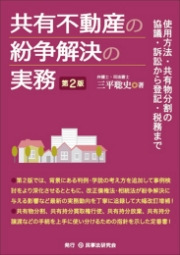【共有物分割完了後の占有権原(合意・債権関係の消滅)】
1 共有物分割完了後の占有権原(合意・債権関係の消滅)
共有物分割により共有関係は解消されます。この時に、それ以前の共有物の利用関係はどうなるのか、具体的には、占有権原はどうなるのか、これも含めて共有者間の合意(債権関係)はどうなるのか、という問題があります。
本記事ではこのことを説明します。
2 分割完了後の占有権原(共有者間の合意・債権関係)(まとめ)
共有物分割が完了した後に、従前の占有権原などはどうなるのか、結論は少し複雑です。最初に結論を表にまとめます。
<分割完了後の占有権原(共有者間の合意・債権関係)(まとめ)>
あ まとめ
共有持分権による占有権原(共有者間の合意)
消滅(終了)する(後記※1)
第三者の占有権原
対抗力の有無と分割類型により定まる(い)
(※1)自己借地権が成立している場合には、第三者の占有権原と同じ扱いになる
詳しくはこちら|自己借地権の基本(混同回避の趣旨・種類・認める範囲)
い 第三者の占有権原
―
対抗力のない占有権原
対抗力のある占有権原
全面的価格賠償
存続
存続
現物分割
存続
存続
換価分割
実質消滅(後記※2)
存続
(※2)新たな所有者(買受人)に対抗できなくなる。ただし、法定地上権が成立する場合は(当然)対抗できる。
詳しくはこちら|形式的競売における法定地上権の適用の有無
この表の内容については、以下、順に説明します。
3 共有解消による共有者の合意の終了(債権関係の消滅)
(1)理論
まず、共有物の使用や管理の方法などについて共有者として合意(決定)した内容は、共有関係の解消により終了(消滅)します。このような合意(債権関係)は共有関係が前提となっているので、共有関係が解消されるとともに終了するのです。当然すぎるのであまり議論にすらならない理論です。
なお、共有者間の協議や合意がなく、共有者Aが共有持分権を占有権原としている状況でも、Aが共有持分権を喪失すれば、言うまでもなく占有権原は消滅します。
共有解消による共有者の合意の終了(債権関係の消滅)
あ 共有物の使用収益の合意→共有存続が前提
ア 平成10年最判
共有者は、共有物につき持分に応じた使用をすることができるにとどまり、他の共有者との協議を経ずに当然に共有物を単独で使用する権原を有するものではない。
しかし、共有者間の合意により共有者の一人が共有物を単独で使用する旨を定めた場合には、右合意により単独使用を認められた共有者は、右合意が変更され、又は共有関係が解消されるまでの間は、共有物を単独で使用することができ、右使用による利益について他の共有者に対して不当利得返還義務を負わないものと解される。
※最判平成10年2月26日
イ 平成30年東京地判
本件建物の所有者(注・土地共有者の1人)が無償で本件土地を利用し、本件土地の公租公課を負担する旨の合意が黙示的に成立したと認められる・・・
本件合意に係る被告Y1の使用権については、地上権又は賃借権的な性質を有するものと解することはできず、あくまで共有関係が継続する限りにおいて存在するものであり・・・
※東京地判平成30年10月11日
い 共有者間の債権関係→共有存続が前提
・・・他の一つは、分割以外の債権関係である。
例えば、その物の管理につき、ある者が他の共有者よりも多くの負担をするという合意がなされているような場合、この債権はどうなるか。
共有関係が一括清算される裁判上の分割の場合には、その債権存立の基盤である共有関係が消滅すれば、その債権も消滅すると考えられる・・・
(注・共有関係を存続させる分割のテーマの前提として)
※新田敏稿『共有物の裁判上の分割の機能と効果』/『法学研究70巻12号』慶應義塾大学法学研究会1997年12月p35
(2)典型例
前述のように、共有物分割が完了した後は、共有者間の合意も共有持分権による占有(権原)も解消される、というのが結論です。具体例を挙げた方が分かりやすいです。AB共有の土地をA(だけ)が使用している状況を想定します。典型例はAが建物を所有している状況です。
土地の共有物分割が終わると、共有持分権を占有権原として占有していた状況は終わります。もちろん、分割の結果Aが取得した(所有することになった)土地については(所有権という)占有権原がありますが、Aが取得しない限り、建物収去土地明渡の義務を負います。
なお、仮にAがBに土地の使用対価を支払っていた(借地という認識でいた)としても、自己借地権にあてはまらないので、混同が適用され、借地関係(土地の賃貸借)としては認められません。
詳しくはこちら|自己借地権の基本(混同回避の趣旨・種類・認める範囲)
結局、この設例のAは何が何でも自身が取得する全面的価格賠償を実現しなくてはならないというのが実情なのです。
共有持分権による占有ケースにおける分割後の状況
あ 設例
建物A所有
土地AB共有→共有物分割
共有土地をAが占有している占有権原はAの共有持分権である
(AB間で協議、合意をしてもしていなくても同じである)
い 分割後の占有権原の有無
分割の内容
占有権原
全面的価格賠償・Aが取得
Aの所有権が占有権原となる(当然)
全面的価格賠償・Bが取得
Aは占有権原を持たない
現物分割
B単独所有の土地(新たな筆)についてAは占有権原を持たない
換価分割
Aは占有権原を持たない(後記※3)
(※3)法定地上権が成立すれば占有権原となるが、この権利関係では法定地上権の成立は否定するのが一般的である
詳しくはこちら|共有と法定地上権の成否(全体像と共有者全員による抵当権設定)
4 共有物分割の法的性質(前提)
次に、共有物を対象とする第三者の利用権原について説明しますが、その前提として、共有物分割の法的性質を押さえておきます。
共有物分割の分割類型は3種類がありますが、(共有持分権や所有権の)売買または交換である、つまり特定承継です。
共有物分割の法的性質(前提)
5 第三者の対抗力のない占有権原の行方→換価分割だけ対抗不可
(1)全面的価格賠償・現物分割
前述のように共有物分割による物権変動は特定承継なので、対抗力のない占有権原は対抗できなくなるのが原則です。ただし、全面的価格賠償や現物分割では通常、もともと貸主(契約の当事者)であった者が新たな所有者となっています。そこで、結論としては対抗力のない占有権原でも対抗できることになると思われます。
たとえば、AB共有の土地について使用貸借がなされ、ABが貸主、Cが借主であるケースで、AがBの持分を取得した(全面的価格賠償)ことを想定します。B持分の売買として考えると、Cの使用借権は買主Aに対抗できないはずです。しかし、もともとAは貸主(使用貸借の当事者)なので、AC間では契約が及んでいるため、Cの使用借権はAに対抗できる結論になると思われます。
この点、仮に、60%の持分を有するBだけが使用貸借の意思決定をしてCとの間で使用貸借をした(Aは契約当事者になっていない)場合には、この理論はストレートには成り立ちません。しかしAは「契約当事者ではないが契約の存在を否定できない立場」にありました。
詳しくはこちら|共有不動産の賃貸借契約における賃貸人の名義(反対共有者の扱い)
そこで、契約当事者であったのと同じ結果になる、という解釈も十分ありえます。
(2)換価分割(形式的競売)→売買は賃貸借を破る
前述の設例において、換価分割となり共有物全体としての売却がなされた場合、新たな所有者(買受人)Dは、従前の使用貸借契約当事者ではありません。そこで、CはDに対して使用貸借契約に基づく占有権原を対抗できません。特定承継(売買)は賃貸借(債権関係)を破る、ということわざどおりです。
(3)形式的競売で共有者が取得したケース→全面的価格賠償類似
では次に、換価分割となり、競売で共有者Aが(共有物全体を)取得した場合はどうでしょうか。主体(人)に着目すると、新たな所有者は貸主(使用貸借契約の当事者)です。そこで、Cは使用貸借による占有権原を対抗できることになるはずです。ちょうど、全面的価格賠償でAがB持分を取得したのと同じような状況です。
ただ、この場合、競売手続では買受人に対抗できる占有権原なしという前提で入札が行われているはずです。買受人が誰かによって占有権原の有無が異なるとすれば、入札の公平性が崩れてしまうという問題があります。
6 第三者の対抗力のある占有権原の行方→オール対抗可能
第三者の占有権原に対抗力がある場合については単純です。もともと(一般論として)特定承継があっても、占有権原を新たな所有者に対抗できます。
たとえば、登記(その他の代用対抗要件)を備えた賃借権です(民法605条)。
7 現物分割の後に存続する占有権原の特殊性→部分的解除可能(参考)
賃貸借や使用貸借の対象の共有物が現物分割となっても、前述のように、その後も占有権原(契約)は存続します。たとえば賃貸借契約そのものは現物分割によって変化することはなく、全体を対象とする1個の契約のままです。しかし、物理的には複数に分かれたことにより、物理的な一部(分割後の1筆の土地)だけを対象とする解除を認めた実例もあります。
詳しくはこちら|賃貸借の対象不動産(貸地)の現物分割後の解除
8 平成3年東京高判が示した根拠不明の利用権原
(1)形式的競売の後の意思解釈による利用権原(平成3年東京高判)
換価分割判決の後の形式的競売で共有者の1人が買受人となったケースについて、その後の占有権原の有無が問題となった特殊なケースの裁判例を紹介します。
競売前の状態としては、土地XA共有、建物YA共有という状態で、土地を対象とする賃貸借や使用貸借の契約はありませんでした。Yは土地の占有権原を持っていません。土地の占有権原はAの共有持分権である、という状況です。
そして土地(だけ)について共有物分割がなされ、換価分割の判決となり、競売が行われました。競売の結果、Xが土地を取得しました。
このケースでは、法定地上権の存否が問題となりましたが、これは、一般的な解釈を前提とすると否定されることになります。実際にこの裁判例でも法定地上権は否定されました。
詳しくはこちら|形式的競売における法定地上権の適用の有無
では、分割前に存在した、Aの共有持分権という占有権原はどうでしょうか。競売の後にはAの共有持分はなくなっているので、当然ですが、Aには占有権原はないことになります。
しかし、この裁判例は、土地利用権原が認められる可能性があるかのようなことを述べています。ただし、土地の明渡請求を否定する、というような具体的な法的効果に結びつけたわけではなく、いわゆる傍論です。
形式的競売の後の意思解釈による利用権原(平成3年東京高判)
あ 事案
ア 権利関係(物権レベル)
建物→Y・A共有
土地→X・A共有→形式的競売(→買受人X)
イ 占有権原
競売前にXは「Y・Aが土地を使用すること」を許容していない
Y・AはAの共有持分権に基づいて土地を占有している状態であった
い 法定地上権→否定(前提)
裁判所は、法定地上権の成立を否定した
詳しくはこちら|形式的競売における法定地上権の適用の有無
う 意思解釈による土地利用権原
・・・本件土地について本件建物のための法定地上権の成立は認められないことに帰するが、建物の存在する共有土地について共有物分割としての競売を行う当事者の合理的意思解釈からすれば、右競売の結果建物と土地の所有者を異にするに至ったからといって、当然に建物のための土地占有権原が失われるものとは解されない。
※東京高判平成3年9月19日
え 土地利用権原の判断の位置づけ
この裁判例で請求されていた内容(訴訟物)は法定地上権が存在しないことの確認(請求)である
意思解釈による土地利用権原は傍論という位置づけである
(2)平成3年東京高判への批判
前述のように、平成3年東京高判には、土地の占有権原が認められる可能性があるかのような記載がありますが、その根拠があるとは思えません。個別的な事情により、土地明渡請求を否定したいのであれば、権利の濫用などの一般条項を使うしかない、という指摘もなされています。
平成3年東京高判への批判
あ 不動産執行の理論と実務→利用権原の内容の欠如
(注・土地AB・建物Aで土地全体の競売について)
ただし、後に共有物分割のための形式競売(民258条、民執195条)がなされたとき、土地利用権がどうなるかについては、法定地上権が成立するとの説、成立しないとの説、成立しないけれども当然に土地利用権原が失われるものでもないとする説(注)、などが考えられる。
・・・
(注)東京高判平3・9・19判夕781号231頁は最後の説のように述べるが、具体的にどのような土地利用権原を想定しているのかは明らかでない。
※東京地裁民事執行実務研究会編著『改訂 不動産執行の理論と実務(上)』法曹会1999年p267、268
い 並木茂氏見解→占有権原否定
なお、本判決は、Yは土地を建物についての自己の持分に基づいて従前どおり利用することができると判示するようであるが、Yの本件土地の利用は事実上のものにすぎないであろう。
それにもかかわらず、XはYに対して本件土地使用の対価(または損害金)を請求しえないから、Xにとって法定地上権が成立した場合より不利になるおそれがある。
・・・
ただ本判決は、「建物の存在する共有土地について共有物分割としての競売を行う当事者の合理的意思解釈からすれば、右競売の結果建物と土地の所有者を異にするに至ったからといって、当然に建物のための土地占有権原が失われるものとは解されない」と苦渋に満ちた判示をしている。
しかし、率直にいえば、Aには本件建物のために本件土地を占有する正当な権原はないというべく、Xの建物収去土地明渡請求に対しては、AおよびYは、せいぜい権利濫用を主張するほかに手がないのではないだろうか。
※並木茂稿『土地およびその上の建物双方の共有者の一人の土地の持分のみが強制競売の売却により第三者の取得に帰した場合における法定地上権の成否(消極)』/『金融法務事情1337号』1992年11月p16、17
う 田中克志氏指摘→理解苦悩
具体的には、乙の従前の敷地持分権に基づく利用相当の利用権原が存続するということなのであろうか。
※田中克志稿/『判例評論403号』判例時報社1992年9月p27
(3)平成3年東京高判に対する私見→分割段階の問題
当事務所としても、前述のように、理論的に整理すると、平成3年東京高判の事案では、競売の後に占有権原はないと考えます。仮に、個別的な事情により居住を保護したい、明渡請求を否定したいと考えるのであれば、それは共有物分割訴訟の段階で、分割方法の判断に反映させるべきであると思います。そのような指摘をする見解もあります。
詳しくはこちら|建物収去を回避するための土地の全面的価格賠償の選択
逆に共有物分割訴訟として換価分割を選択したということは、居住は保護されないということが許容されている、と考えるほうが合理的であると思います。
さらに、競売において買受人が誰かによって占有権原の有無が違ってくるというのも、競売手続の公平性の点から問題があるとも思います。
本記事では、共有物分割完了後の占有権原や共有者間の合意の問題を説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に共有不動産や共有物分割に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。