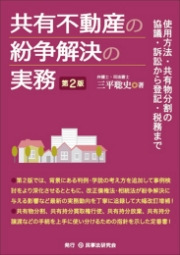【複数の借主(賃貸借・使用貸借)のうち1人が所在不明であるケースの解決方法】
1 複数の借主(賃貸借・使用貸借)のうち1人が所在不明であるケースの解決方法
借地契約では、借主(借地人)が複数人であることがあります。典型例は借地上の建物がABCの共有となっているケースです。ここで、借主ABCのうちAの所在が不明である場合に、Cを買主から外す(ABだけが借主となる)方法や借地権(と建物)を第三者に売却するためのいくつかの方法があります。
借地ではない土地の賃貸借、また、建物や動産の賃貸借の場合、さらに使用貸借の場合で、可能な方法は異なります。
本記事では、複数の借主の1人が所在不明のケースでとることができる手続について横断的に説明します。
2 法的問題の分類
法的問題は2つに分類できます。
(1)持分処分権限
共有者Aの所在が不明なので、そのままではAの賃借権などの(準)共有持分を別の者に譲渡することができません。
裁判所に不在者財産管理人を選任してもらえば、その管理人がAの共有持分を譲渡(売却)することが可能になります。この方法は単純ですが、管理人の報酬支払が必要となってしまいます。
詳しくはこちら|不在者財産管理人の制度の全体像(選任要件・手続・業務終了)
令和3年の民法改正で、裁判所の決定で所在不明の共有者の共有持分を他の共有者が買い取ること、(共有不動産全体として)第三者に売却することができるようになりました。
詳しくはこちら|所在等不明共有者の不動産の共有持分取得手続(令和3年改正)
所在不明共有者の持分譲渡権限付与裁判
詳しくはこちら|所在等不明共有者の不動産の共有持分譲渡権限付与手続(令和3年改正)
管理人を選任しないで済むので、継続的に報酬がかかるということを避けられます。
(2)解除問題
以上のいずれかの方法でAの賃借権の準共有持分を移転することに成功しても、別の問題があります。たとえば、賃借権の譲渡として賃貸人(地主など)に賃貸借契約を解除されることがあるのです。
これについては、もともとの(複数人の)賃借人の間の譲渡であれば解除はできない傾向が強いです。
詳しくはこちら|特殊な事情による賃借権の移転と賃借権譲渡(共有・離婚・法人内部)
また、地主の承諾の代わりに裁判所の許可を得る制度もありますが、これが使えるのは借地(建物所有目的の土地の賃貸借)だけです。借地の場合は裁判所の許可をとれば安全かというと、ここでも、所在不明のAが申立人になれないという問題が出てきます。
これについて、もともとの(複数人の)賃借人の間の譲渡であれば、譲渡人(A)は申立人にならなくてよい、という見解も提唱されています。
詳しくはこちら|借地権譲渡許可の裁判の申立人と申立時期
3 貸主(賃貸人など)の同意ありケース・まとめ
以上のように、理論は複雑なので、以下、いろいろなパターンについて、持分取得裁判と持分譲渡権限付与裁判を使えるかどうか表にまとめます。
最初に賃貸人や使用貸主が譲渡について同意しているケースについてまとめます。
これは簡単です。不動産(の用益権)であれば両方の裁判手続を使えます。
動産は2つの裁判手続は使えません。
貸主(賃貸人など)の同意ありケース・まとめ
「取」=持分取得裁判
「譲」=持分譲渡権限付与裁判
なお、前述のように、どのパターンであっても、不在者管理人の選任の手続は使えます。ただし、管理人報酬がかかることになってしまいます。
4 貸主(賃貸人など)の同意なしケース・まとめ
次に、貸主が同意してくれないケースで使える手続をまとめます。
まず、前記と同様に、2つの裁判手続が使えるのは、不動産(の用益権)だけです。
裁判手続で決定を得てAの賃借権(の準共有持分)を譲渡できたとしても、賃貸人が同意していないので解除されるのが原則です。ただし、賃借人がABCであるケースで、AがCに賃借権(の準共有持分)を譲渡しても、解除は認められない傾向があります。
この点、第三者(ABC)以外の者に譲渡した場合には、この例外扱いはありません。つまり解除されることになります。持分譲渡権限付与の裁判は使えないということになります。
貸主(賃貸人など)の同意なしケース・まとめ
「取」=持分取得裁判
「譲」=持分譲渡権限付与裁判
(※1)既存の共同賃借人間での賃借権(の準共有持分)の譲渡は賃貸人の承諾は不要となる(解除は否定される)傾向がある(前述)
(※2)地主の承諾に代わる裁判所の許可を得る方法もある。ただし、借地権の譲渡人(所在不明共有者)の関与なく申立ができるかどうか、という問題がある(前述)
(※3)結論としては、賃貸借の場合(前記※1)と同じことになると思われる(後述)
5 パターン別の具体例
(1)借地=建物所有目的の土地の賃貸借
借地、つまり、建物所有目的の土地の賃貸借のケースで、借地人(賃借人)がABCの3人である場合、ABCは(建物と)借地権を(準)共有していることになります。
借地権は不動産(土地)の用益権(賃借権)なので、持分取得裁判と持分譲渡権限付与裁判の対象になります。
借地権(賃借権)(の準共有持分)をAからBに譲渡する場合、地主は無断譲渡を理由とした解除はできない傾向が強いです。
仮に、解除できるような状況であった場合、Bは裁判所に、地主の承諾に代わる許可を求めることができます。この点、原則としてAも申立人になる必要がありますが、Aは所在不明なので申立人になることができません。この場合にはAは申立人にならなくてもよい、という見解もあります。
なお、持分譲渡権限付与の裁判を使って、ABCが建物と借地権を第三者Dに売却する場合には、地主からの解除を否定できません。裁判所の許可を得ようとしても、このケースではAも申立人になることを回避するような解釈はないと思われます。第三者に売却したいのであれば、まずは持分取得裁判でBCだけの共有としてから、次にBCが第三者Dに売却し、この売却について裁判所の許可を得る、というように2段階に分けるしかないです。手間が増えますし、承諾料(裁判所が定める対価)も2重にかかる、ということになってしまいます。
(2)借地以外の不動産賃貸借
不動産の賃貸借のうち、借地以外のものについて考えます。
これにあたるものは、まず、土地賃貸借のうち建物所有目的以外のもの、具体例は駐車場、資材置場、太陽光パネル用地などとしての土地賃貸借があります。また、建物の賃貸借もこれにあたります。
これらは不動産の用益権なので賃借人の1人が所在不明である場合には持分取得裁判、持分譲渡権限付与裁判が使えます。
これとは別に、賃貸人に無断で賃借権を譲渡した場合、解除されることになります。ただし、賃借人ABCの中の譲渡であれば解除は認められない傾向があります。
なお、(地主の承諾に代わる)裁判所の許可の制度は借地限定なので、借地以外の賃貸借契約では使えません。
結局、第三者への譲渡は解除されるのでこの手法は使えず、共有者間の譲渡(持分取得裁判)だけが使えるという結論です。
(3)不動産の使用貸借
以上は賃貸借の設例でしたが、不動産の使用貸借について考えます。まず、持分取得裁判、持分譲渡権限付与裁判のいずれも、不動産の用益権(の準共有持分)について使えます。使用貸借(使用借権)であってもこの2つの裁判手続は使えます。
次に、使用貸借では、「第三者に借用物の使用又は収益をさせる」には「貸主の承諾」が必要です(民法594条2項)。これに違反すると解除されます(民法594条3項)。
借主がABCであるケースで、Aの使用借権をBに譲渡した場合、「第三者に使用させた」ことになるでしょうか。Bはすでに借主なので「第三者」にはあたらないという判断になる可能性が高いと思われます。
そこで、持分取得裁判を使うことは可能という方向性になります。
一方、第三者(ABC以外の者)に譲渡することは「第三者に借用物の使用又は収益をさせる」にあたり、解除されると思われます。つまり、持分譲渡権限付与の裁判は使えないということになります。
(4)動産の賃貸借・使用貸借
以上はすべて不動産の貸借(賃貸借・使用貸借)の設例でした。最後に、動産の賃貸借や使用貸借のケースについて考えます。
持分取得裁判、持分譲渡権限付与裁判のいずれも、不動産の用益権だけが対象です。動産の用益権は対象外です。これらの手続は使えません。
(5)組み合わせの事例(土地賃借権(借地以外)+動産)
たとえば、ABCが土地を賃借して太陽光パネルを所有、運用しているケースでAの所在が不明である場合、土地の賃借権をBに譲渡することや、第三者に売却することについては、2つの裁判のどちらかにより実現します。しかし、太陽光パネル本体は動産なので、動産の共有持分を譲渡することは2つの裁判では実現しません。
この設例では、(コストがかかってしまいますが)不在者財産管理人の選任の手法を使うしかない、ということになります。
なお、BCが土地賃借権の準共有持分と太陽光パネル(動産)の共有持分を第三者Dに売却することで、とりあえず、Dが過半数持分権者として太陽光発電を運用できるようにする、という方法もあります。この方法は賃借権譲渡について賃貸人の承諾を得ることが前提となります。
(高須順一稿/潮見佳男ほか編著『Before/After民法・不動産登記法改正』弘文堂2023年p68、69参照)
ただし、太陽光発電設備の運用が民法上の組合に該当する場合、組合財産の共有持分の譲渡はできません。
詳しくはこちら|民法上の組合の財産の扱い(所有形態・管理・意思決定・共有の規定との優劣)
この場合、解散の手続をとる必要があります(民法683条)。具体的には、組合員(共有者)の頭数の過半数で清算人を決めて、清算人が売却するという方法です(民法685条)。
本事例では、裁判所の手続を使わずにBCだけで売却できるということになります(賃貸人の承諾が必要ということは同じです)。
6 貸主の1人が所在不明のケース(参考)
本記事のテーマから外れますが、(借主ではなく)貸主が複数であるケースについても触れておきます。
たとえばABC共有の建物について、ABCが賃貸人、第三者Eが賃借人となって入居しているケースです。収益物件が共有となっているよくあるケースです。
Aの所在が不明である場合、持分取得裁判も持分譲渡権限付与裁判のいずれも使えます。
持分譲渡権限付与裁判を使い、建物の所有権をDに売却したことを想定します。賃借人Eは対抗要件(引渡)を得ているので、Eの承諾がなくてもEは賃貸人の地位を承継します(民法605条の2第1項)。そして、Eは所有権移転登記を得たうえで、Dに対して賃料請求をすることになります(民法605条の2第3項)。
本記事では、複数の借主のうち1人が所在不明であるケースにおける解決方法について説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に不動産の賃貸借や使用貸借に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。