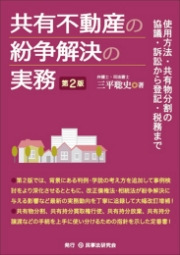【土地明渡請求訴訟における建物買取請求権行使のタイミング(時機遅れ・判決確定後の行使)】
1 土地明渡請求訴訟における建物買取請求権行使のタイミング(時機遅れ・判決確定後の行使)
借地契約の期間満了において、地主が更新拒絶をして土地の明渡請求をするケースは多いです。更新が認められない場合には、借地人は建物買取請求権を行使する、という対応があります。
詳しくはこちら|借地期間満了時の建物買取請求権の基本(借地借家法13条)
この建物買取請求は主張(行使)するタイミングが問題となります。本記事ではこのことを説明します。
2 建物買取請求権の主張が遅くなる傾向(構造)
借地人による建物買取請求が認められるのは、前述のように更新されない場合です。法定更新がされている、と主張(反論)している段階では極力、建物買取請求の主張をしてくないのです。そこで、たとえば地主からの明渡訴訟の中盤や終盤で初めて建物買取請求の主張をする、ということがよくあります。
さらに、借地人が勝訴する(更新される)と強く思っていた場合には、判決まで建物買取請求の主張をしないこともあります。この場合に敗訴(明渡請求を認める)判決が出てしまった場合、その後で建物買取請求をする、というケースもあります。
このように、性質上遅らせる傾向があるので、タイミングの問題が出てきてしまうのです。
3 建物買取請求の主張の時機遅れ却下→実例あり
(1)昭和46年最判・時機遅れによる建物買取請求権の却下
昭和46年最判の事案では、地主が明渡請求訴訟を提起し、その第2審の終盤で借地人が建物買取請求の主張を出しました。これについて最高裁は時機に遅れた主張であるとして、建物買取請求を認めませんでした。
前述のように建物買取請求の主張が遅れてしまうことは仕方ないのですが、この事案では、それにしても遅すぎたといえます。
昭和46年最判・時機遅れによる建物買取請求権の却下
あ 原審判断→建物買取請求権の主張の却下
(注・第三者の建物買取請求権について)
・・・原審は、上告人Aが原審第一一回口頭弁論期日(昭和四四年九月九日)に提出した所論建物買取請求権に関する主張を、同第一二回口頭弁論期日(同年一〇月二三日)に民訴法一三九条一項により却下して弁論を終結し、原判決を言い渡したことが認められ、右却下の決定が右民訴法の規定の定める要件の存在を認めたうえでなされたことも明らかである。
い 「時機遅れ」の判断
ア 事案内容
そして、上告人Aが第一審において口頭弁論期日に出頭せず、本件建物収去、土地明渡等を含む一部敗訴の判決を受けて控訴し、原審第二回口頭弁論期日(昭和四二年九月二一日)に、抗弁として、同上告人が前借地人から地上の建物を買い受けるとともに、賃貸人の承諾を得て本件土地の賃借権の譲渡を受けた旨主張したが、被上告人ら先代においてこれを争つていたこと、その後証拠調等のため期日を重ねたが、前述のとおり、第一一回口頭弁論期日にいたつてようやく建物買取請求権行使の主張がなされるにいたつた等本件訴訟の経過によつてみれば、右主張は、少なくとも同上告人の重大な過失により時機におくれて提出されたものというべきである。
原審においては二度和解の勧告がなされたが、口頭弁論期日もこれと平行して進められたのみならず、和解の試みが打ち切られたのちも、第八回以降の口頭弁論期日が重ねられ、上告人Aにおいて十分抗弁を提出する機会を有していたことから考えると、和解が進められていたから前記主張が提出できなかつたという所論は、にわかに首肯することができない。
つぎに、本件記録によれば、所論建物買取請求権の行使に関する主張は、被上告人らが借地法一〇条所定の時価として裁判所の相当と認める額の代金を支払うまで、上告人らにおいて本件建物の引渡を拒むために、同時履行等の抗弁権を行使する前提としてなされたものであることを窺うことができるが、所論指摘の各証拠によつては到底右時価を認定するに足りるものとは認められず、かくては右時価に関する証拠調になお相当の期間を必要とすることは見やすいところであり、一方、原審は、本件において、前述のように右主張を却下した期日に弁論を終結しており、さらに審理を続行する必要はないとしたのであるから、ひつきよう、上告人Aの前記主張は、訴訟の完結を遅延せしめるものであるといわなければならない。
イ 結論→時機遅れ肯定
それゆえ、原審が右主張を民訴法一三九条一項により却下したのは相当である。
※最判昭和46年4月23日
(2)昭和46年最判の評釈・工藤敏隆氏見解→賛成
工藤敏隆氏は、昭和46年最判の判断について、賛成する趣旨のコメントをしています。
昭和46年最判の評釈・工藤敏隆氏見解→賛成
あ 建物買取請求権の抗弁提出が遅くなる傾向(構造)
要件①および②について、建物買取請求権は、相殺と同様に自己の主張(占有権原である借地権)を犠牲にする抗弁であることから、一般に早期の提出を期待できないとする見解がある(新堂・前掲528頁、松本博之=上野𣳾男『民事訴訟法〔第8版〕』[2015]393頁〔松本〕など。反対説として、斎藤秀夫ほか編著『注解民事訴訟法(3)〔第2版〕』[1991]500頁〔斎藤秀夫=井上繁規=小室直人〕、秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法III』[2008]340頁)。
い 判例の判断の評価→賛成
しかし、この見解を採っても、本件では控訴審第2回期日で本件土地賃借権譲渡が主張され、その証拠調べ等のために期日が重ねられていたこと、第11回期日で行われた建物買取請求権行使の主張が第12回期日で却下され同期日に結審したこと、および、和解の試みが第8回期日までに打ち切られていたことからすれば、要件①(注・「時機に遅れた」)および②(注・故意・重過失)の認定は可能であろう。
※工藤敏隆稿/『民事訴訟法判例百選 第5版』有斐閣2015年11月p99
4 土地明渡請求訴訟判決確定後の建物買取請求権行使→可能
(1)昭和52年最判・既判力による遮断→否定
地主からの明渡訴訟に対して、借地人がその訴訟の中では建物買取請求の主張をしなかったという事案についての判例があります。いずれも、明渡請求を認める判決が確定した後になって初めて借地人が建物買取請求権の行使をした、というケースです。具体的には、明渡請求訴訟とは別の訴訟(請求異議訴訟)を借地人の方から提起しています。
一見、すでに確定した判決を否定するものであるため、判決の既判力によってそのようなことはできないのではないか、という発想があります。
しかし、昭和52年最判は、既判力は及ばない、つまり建物買取請求権の行使を認める、という判断をしました。
昭和52年最判・既判力による遮断→否定
借地上の建物の譲受人が、地主から提起された右建物の収去及び敷地の明渡を請求する訴訟の事実審口頭弁論終結時までに、借地法一〇条の建物買取請求権があることを知りながらその行使をしなかつたとしても、右事実は実体法上建物買取請求権の消滅事由にあたるものではなく、したがつて、建物譲受人はその後においても建物買取請求権を行使して地主に対し建物の代金を請求することができるものと解するのが相当である。
※最判昭和52年6月20日
(2)平成7年最判・既判力による遮断→否定
平成7年最判も、昭和52年最判と同じ判断をしています。詳しい理由を示しています。前訴の内容である借地契約終了(による明渡請求)と、本件(後訴)の内容である建物買取請求権は別個のものである、という判断がポイントです。
平成7年最判・既判力による遮断→否定
あ 結論
(注・期間満了における建物買取請求権について)
借地上に建物を所有する土地の賃借人が、賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結時までに借地法四条二項所定の建物買取請求権を行使しないまま、賃貸人の右請求を認容する判決がされ、同判決が確定した場合であっても、賃借人は、その後に建物買取請求権を行使した上、賃貸人に対して右確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、建物買取請求権行使の効果を異議の事由として主張することができるものと解するのが相当である。
い 理由
けだし、(1)建物買取請求権は、前訴確定判決によって確定された賃貸人の建物収去土地明渡請求権の発生原因に内在する瑕疵に基づく権利とは異なり、これとは別個の制度目的及び原因に基づいて発生する権利であって、賃借人がこれを行使することにより建物の所有権が法律上当然に賃貸人に移転し、その結果として賃借人の建物収去義務が消滅するに至るのである、(2)したがって、賃借人が前訴の事実審口頭弁論終結時までに建物買取請求権を行使しなかったとしても、実体法上、その事実は同権利の消滅事由に当たるものではなく(最高裁昭和五二年(オ)第二六八号同五二年六月二〇日第二小法廷判決・裁判集民事一二一号六三頁)、訴訟法上も、前訴確定判決の既判力によって同権利の主張が遮断されることはないと解すべきものである、(3)そうすると、賃借人が前訴の事実審口頭弁論終結時以後に建物買取請求権を行使したときは、それによって前訴確定判決により確定された賃借人の建物収去義務が消滅し、前訴確定判決はその限度で執行力を失うから、建物買取請求権行使の効果は、民事執行法三五条二項所定の口頭弁論の終結後に生じた異議の事由に該当するものというべきであるからである。
これと同旨の原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
※最判平成7年12月15日
5 明渡訴訟における時機遅れ却下後の別訴での建物買取請求→可能
(1)具体的アクション(前提)
以上のように、建物買取請求については、時機遅れの主張と、別訴による主張という2つの段階での問題があります。ここで、この2つの関係が問題となります。
たとえば、地主による明渡訴訟の終盤で借地人が建物買取請求の主張をして、裁判所が時機遅れとして却下し、明渡請求を認める判決が言い渡されたと想定します。当然借地人としては別訴(請求異議訴訟)を提起して、建物買取請求権を行使したのだから、建物は地主の所有になっている、代金(時価)を請求する、という主張をするのが通常です。
(2)時機遅れ却下後の請求異議訴訟→否定(一般論・前提)
この点、一般論としては、時機遅れとして却下された主張は、その後の請求異議訴訟では主張できない、つまりどちらの訴訟でも使えずに終わる、という扱いがあります。
この一般論をそのままあてはめると、この設例では借地人は請求異議訴訟でも建物買取請求権が認められない、という厳しい状態になってしまいます。
時機遅れ却下後の請求異議訴訟→否定(一般論・前提)
あ 建物買取請求の主張が遅くなる傾向(前提)
(注・東京地判平成13年11月26日について)
(実際、前記のように、一審で勝訴している立場からすると、予備的抗弁を出すことには躊躇されよう。
い 時機遅れ却下後の請求異議訴訟→否定(一般論)
また、その提出が遅れると、時機に後れた抗弁として却下されることがあり〔最判昭46.4.23判時631号55頁〕、口頭弁論終結時までに建物買取請求権を行使していた場合には、これを異議事由として請求異議訴訟を提起することはできないとするのが一般であることからすると、なおさらであろう)。
佐藤陽一稿/『判例タイムズ1154号臨時増刊 主要民事判例解説』2004年9月p18〜
(3)稲葉一人氏見解・時機遅れ却下後の別訴での建物買取請求→可能
建物買取請求権については、前述の一般論がそのままあてはまるわけではない、という見解が一般的だと思います。まず、稲葉一人氏は、「時機遅れによる却下」で封じられるのは「同一手続内」での主張だけなので、別の手続(別訴=請求異議訴訟)で主張することは封じられない、という見解を示しています。
稲葉一人氏見解・時機遅れ却下後の別訴での建物買取請求→可能
あ 結論→可能
平成七年判決が結論するよう(前訴において建物買取請求権が時機に後れたものとして却下されたとしても)後訴においては再度買取請求権は行使できると考えるべきであろう。
い 時機遅れ却下と既判力の違い
つまり、一つの訴訟手続内で提出可能であったかとの判断における当事者の手続保障と、後訴を提起してその中で再度主張をすることを認めるか否かを判断する際の手続保障とは利益状況は異なる。
つまり、前者(注・時機遅れ却下)は、一連の当事者の活動は先行行為が後行行為の前提となり当事者間の信頼の上に成り立っているものであり、これに反して出された攻撃防御方法は信頼関係を破壊し訴訟を遅延させるとして、その訴訟では提出者の手続保障は背後に退き、これを判断するに際しては提出を許さないという手続内判断なのである。
後者(注・既判力)は、既判力の紛争一回解決効から、より類型的に考えられる判断であり、本訴とは別個の紛争において、提出者の負担で新たな訴えを提起し、異議事由等の存否が審理の対象となった手続で、改めてその異議事由等の審査をする際の手続保障が問題となる。
ここでは、遮断することにより、提出者の実体法上の請求権が失われることになるので、提出者の手続保障がより重視される。
このような観点から検討すれば、結論的には、攻撃防御方法の却下における「時機に後れた」かの判断では、具体的な手続保障が要求される(裁判所が釈明権を行使することによりそれより以前に提出の機会が与えられたか否かが具体的に問われる)が、既判力の遮断効を判断の際は、抽象的ないし実体関係的な手続保障を基準とすることになろう。
このように考えれば、本判決を含めた三判決(注・最判昭和46年4月23日、最判昭和30年4月5日、最判平成7年12月15日)の整合性が保たれる(なお、高橋宏志「重点講義民事訴訟法」四一八百以下参照)。
※稲葉一人稿/『法学教室221号』有斐閣1999年2月p30
(4)工藤敏隆氏見解・時機遅れ却下後の別訴での建物買取請求→可能
工藤敏隆氏も稲葉氏の見解に賛同しているように読めます。
工藤敏隆氏見解・時機遅れ却下後の別訴での建物買取請求→可能
※工藤敏隆稿/『民事訴訟法判例百選 第5版』有斐閣2015年11月p99
6 建物「収去」判決による「退去」の強制執行→可能(概要)
ところで、前述のように、建物収去土地明渡請求訴訟と請求異議訴訟の2つの訴訟がなされた場合、執行段階で問題が生じます。
まず前訴の判決の内容は地主から借地人への建物収去土地明渡請求を認めるものです。一方、建物買取請求によって建物は地主の所有になっているので建物収去の執行はできなくなっていて、その代わりに建物から退去させる必要がありますが、判決には建物退去の命令は書いてありません。
理論は複雑なのですが結論としては、この判決で建物退去の強制執行が可能となっています。
詳しくはこちら|建物買取請求権の行使後の建物「収去」判決による「退去」の強制執行(可能)
本記事では、土地明渡請求訴訟における建物買取請求権行使のタイミングについて説明しました。
実際には、個別的事情により法的判断や主張として活かす方法、最適な対応方法は違ってきます。
実際に借地期間満了における更新拒絶など、土地明渡請求に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。