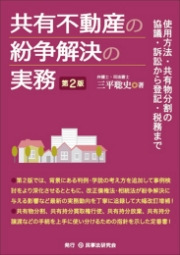【社宅は『対価』によって『借家』となる,公務員の官舎は『借家』ではない】
1 社宅であっても対価支払がある場合は『借家』になる
2 社宅の使用対価が賃料相場と同程度であれば『借家』となる
3 借宅は転勤では退去の必要があるが,転籍では必要ない
4 公務員宿舎は『借家』にならない
1 社宅であっても対価支払がある場合は『借家』になる
社宅に居住している場合は,一般に,雇用主(会社など)との間で社宅使用契約が締結されている状態と考えられます。
仮にこの社宅使用契約が一般の賃貸借であれば,借地借家法が適用になり,解約(更新拒絶)は大幅に制限されます。
つまり,退職後も居住を続けられる可能性が高いです。
借地借家法の適用の有無については,判例などで多くの解釈が蓄積されています。
それらの解釈をまとめると,次のようになります。
<社宅が『借家』にあたるかどうかの判断例>
あ 労務提供との結びつき
社宅使用が従業員の労務提供と密接に結びついている場合
→解雇により社宅の使用権が消滅する合意は有効である
=旧借家法の更新に関する規定の適用が制限されている
※最高裁昭和35年5月19日
※最高裁昭和39年3月10日
い 福利厚生の一環
社宅の提供が従業員に対する福利厚生の一環となっている場合
→借地借家法は適用されない
※東京地裁平成9年6月23日
う 賃料相当の使用料の負担あり
従業員が賃料相当程度の使用料を負担している場合
→借地借家法が適用される傾向がある
2 社宅の使用対価が賃料相場と同程度であれば『借家』となる
一般に社宅に入居する場合,使用料管理費社宅費(控除)などの名目で居住者(従業員)も一定の使用対価を負担するのが通例です。
その金額によって,『借家』として認められることもあります。
借地借家法の適用を認める賃料相当程度の使用対価の解釈は多くの裁判例で行われています。
近隣相場,(運営)経費などが重要な参考データとされます。
<社宅の使用料と『借家』としての認定の関係>
『ア・イ』のいずれかに該当する場合
→借地借家法が適用される傾向がある
ア 賃料と同程度の負担あり
使用対価が一般の民間賃貸住宅における賃料と同程度である
イ 賃料に近い程度の負担あり
使用対価が賃料相場より低いが大幅には変わらない
※東京地裁平成9年6月23日参照
3 借宅は転勤では退去の必要があるが,転籍では必要ない
社宅は,勤務先の業務と一定の関係があります。
具体的には,転勤や転籍で住めなくなるかどうか,という問題です。
(1)転勤の場合,退去が必要である
転勤は勤務地が変更となりますので,従前の社宅に居住する理由は失われましょう。
一般に,社宅使用のルール(契約,規約や黙示の合意)によって,転勤時には社宅を明け渡すことが取り決められているのが通例です。
このようなルールは原則的に有効です。
(2)転籍の場合,退去は必要ではない
転籍は,従前の雇用主との雇用関係は解消されます。
社宅への入居は従業員であることが前提とされています。
結局,転籍した場合は社宅から退去する必要が生じます。
(3)出向の場合,退去は必要ではない
出向は,従前の雇用主との雇用関係は継続します。
従って,従業員であることに変わりはありません。
結局,社宅を退去する必要はないということになります。
ただし,社宅使用のルールで出向時には退去するとなっていた場合は,原則としてこのルールは有効と考えられます。
(4)労働法の観点からの規制は別
なお,実務上は,居住環境に大きな影響を与える転勤・転籍については,有効性が問題となります。
従業員自身が納得していない場合は,転勤・転籍命令自体が無効となる可能性もあります。
これは,借地借家法の適用とは別の問題です。
4 公務員宿舎は『借家』にならない
公務員宿舎は民間企業の社宅に相当する制度です。
しかし,公務員宿舎プロパーの法律があります。
公務員宿舎法です。
この法律によって,居住に関するルールが規定されています。
代表的なものは,明渡に関するものです(18条)。
借地借家法よりも公務員宿舎法が優先されます。
結局,借地借家法の適用はないということになります。